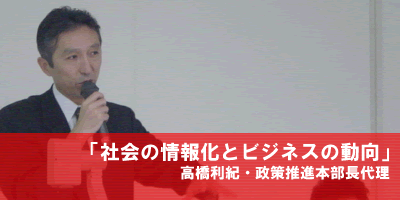
2002年12月17日(火)情報学特別講義III
富士通株式会社 政策推進本部部長代理 高橋利紀
 |
堀田
進め方,評価について説明します。情報学特別講義3。情報化を支えるSEの仕事というのがテーマ。これまでなかった講義科目。受講予定数は130を越えています。この講義の趣旨は,現実の世界で働いている人から講義をしてもらうという趣旨の集中講義が情報学特別講義。学部の学生から見ればみんな割と甘っちょろい。せっかく3日間来ていただくので,真剣に受講してほしいと思う。今回の3日間の講義は,富士通株式会社からいろんな立場の人から来ていただいている。どなたもトップリーダーで忙しい中交渉してやっと実現した講義。
今日はe-Japan計画。国の情報化と,日本と諸外国の関係からビジネスの動向を高橋部長に報告していただく。話していただく。明日は,浜松の支店長。井門支店長。3日目は,現場のSEの仕事をご紹介いただき,どんなスキルが必要か。日程を確実に決めています。時間を守るように。
■午前の部
富士通株式会社 政策推進本部長代理 高橋利紀
 |
高橋
午前中は,コンピュータ,ネットワークをやっている富士通という会社について紹介する。午前中前半では,企業の雰囲気をお話しさせていただいたり,プロジェクトXで取り上げられたところを見ていただく。午前中後半では,社長や会長が話す内容を紹介しながら、技術がこんな風に進んできていて,これから大事なのは使い方という話をする。一般のお客様に話していること。午後は,政策推進本部で関わっている国の政策や仕組み,e-Japan計画や課題についてお話する。
私は1974年に富士通に入って,28年勤めている。あと少しで30年。1979年から4年間くらいニューヨークの駐在事務所で勤務した。富士通はIBMと激しい競争をしているので,NY地区でIBMの情報を収集していた。戻ってきてからは政府の施策関係やインターネットをはじめとしたネットワーク関係に携わってきた。
最近強烈に感じることは、企業が大学の先生と一緒にやることが多いということ。堀田先生とは2000年くらいからおつきあいをさせて頂いている。元IBM会長のガースナーが力を入れているのが,一般の小中学生に情報リテラシーをつけること。私どもの会社の会長もその辺をやりたいということで,ご協力をお願いして2000年,2001年と全国の小中学校の先生たちとプロジェクトをやった。昨年にはインターネット博覧会に参加し,12ヶ月やって14個くらい文部大臣賞をいただいた。他にもIT担当大臣や協議会の先生からも表彰いただいた。大事なのは,技術があるけれどそれをどう使っていくか。今年はIETFという全世界の技術者が集まる会議が夏に横浜で開催されるというので,慶応の村井教授と協力し,富士通はスポンサーとして参加した。企業としては研究なり実践を積み重ねている先生との交流を始めている。
今でこそグループ従業員16万人で売上5兆円くらいの会社だが、昭和40年代前半は業界でも下から数えたほうが…という時代が長かった。富士電機という富士通の親会社,さらにその上に古河グループというのがあって,グループの中心が古河工業という会社。戦争が終わってから,財閥解体の動きの中で,古河工業の岡田完二郎という人がパージにあって、子会社の富士電機のさらに下、富士通の前身である会社の社長におとされた。そのときは1500人くらい。富士通のコンピュータのはじまりは,日立やNECや沖電気と同じことをやっていたのではだめだ,ということで思い切ってやってみろという岡田さんの指針。それから池田という技術に夢中な男がいて,この2人が富士通のコンピュータの基礎を作った。
現在は、産業界が非常に不況で,七転八倒の苦しみをしている。企業も旗色が悪いとめちゃくちゃたたかれる。ここをどう乗り切るかを考える上で,プロジェクトXに私が売り込みをして,富士通のDNAを若い社員にも見せてやりたいと思った。1974年は私が学部卒で富士通に入った年であるが,その年の11月に池田さんが亡くなった。社内で池田さんをみかけた人は私の代が最後であると思う。
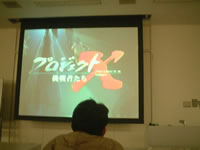 |
ビデオ上映 「NHKプロジェクトX『第83回・国産コンピュータゼロからの大逆転』」
http://www.nhk.or.jp/projectx/83/index.htm
今は、オープンアーキテクチャになる中で,自分たちで作り上げた技術がなくていいのだろうか,という話が我々産業界だけではなくて,国としても考えられている。たとえばヨーロッパはMicrosoftやUNIXのライセンスを米企業がもっていることに対してNational Securityの観点から問題視している。ドイツ政府はオープンシステムや国産コンピュータを使うことを指定したり,中国では昭和30年代に日本がやってきたような中国発のコンピュータを作ろうというような動きがある。
結論的に言うと,自分で考えないとだめ。全員が全員コンピュータのOSや回路設計をするということではないが,日本の今までのアドバンテージは池田敏雄のような人が自分でコンピュータを作ったように、まず自分で考えるところから始めた。それが日本の競争力の原点だったと思う。
富士通の事業戦略として3つある。1つは,ソフトサービスに成長を求める。2つ目は,コアテクノロジーに集中していく。特に最先端のデバイスや光技術,信頼性,DWDM等。3つめとして,グループ全体の競争力強化がある。
事業構造については、電子デバイスの技術がまずある。その上のプラットフォームというのがコンピュータのCPUや周辺装置。さらにその上にサービス。SEの部隊を中心に展開。デバイスからサービスまで持っているのを富士通の強みにしていく。Everything on the Internetとは、「すべての技術をインターネットに」ということ。
連結の対象として,商法上記載してある会社が国内で173社,海外で367社がある。これらの会社を富士通が統合しコントロールしている。
今日の議題は,最終的にはプロジェクトXじゃないが「人」である。できあがった「もの」より,無限の可能性があるのは「人」。当たり前といえば当たり前だが,企業を最後に支えるのは人材。各企業はどれだけよい人材を集めるかがポイント。大学も、北京の大学にしても,米国の大学にしても,どれだけいい人材を育てられるかはすごい競争になっている。欧米ではいい学生を集めるためにお金を出すと言っているくらい。
 |
モノを作るコストは海外の方が安い。日本の場合は世界的な給与水準からみればトップレベルに近い。給料は生活に関わってくるので,いきなり安くするわけにはいかない。日本の企業は一度あがった給与の体系をひっぱっていく必要がある。海外では日本の給与の10分の1くらいで働く。ひとりひとりの性能は日本の学生がいいかもしれないけれど,向こうは人数が多い。そうなったらモノ作りで勝てない。国内では,先月まである工場でプリンタ板をつくっていた人を,営業やSEやその他の関連会社の保守をやっている人に職種転換している。
成果主義の話。私は1年に1度だが、石井と内山は年に何回か上司と成果報告をする。事前に目標をきめて,6ヶ月くらいして上司が評価する。だいたいみんな自分はよくやったという。しかし上から見ると違う,というふうになったりする。私もやってみて,人の評価をするのは嫌な仕事だと思うけど,それをどんどんこなしていく必要がある。目標を高くする必要がある。目標を低くすると会社としては負けてしまう。僕も偉くなればなるほど楽になるかなと思ったけど,なかなか大変。たとえば,阪神タイガースをAクラスに入れるとコミットして監督しているようなもの。Aクラスに入れなかったらクビ。人が人を公正に評価することは不可能に近い。だけどそれは企業の場合には最終的に評価の仕組みが悪ければ,competitorに負けてしまう。そういう制度がよければ会社は利益を出せるはず。利益を出して配当を出して,次の開発に循環させられるようになるまでこういう制度は試行錯誤でやっていく。
ITの活用。スピードと効率。情報化投資ということで売り上げの2%を情報化に投下していきたい。
ソフトウェアの開発生産性の向上。これがものすごい悩み。ソフトウェアの開発はものすごい勢いでふくらんでいるが追いつかない。ハードウェアの性能は,半導体のチップに今までより細い線を書けるようにすること。ソフトウェアはなかなか出来ない。人に依存しているから,2割,3割性能をあげるのも難しい。ハードウェアみたいに,急に4倍の性能というのはできない。ソフトウェアをどんどん作ってバックログができているというのが現在の課題。これに解を求められれば億万長者にも何にでもなれる。
マネジメントの課題としては,今ITのハードウェアだ,ソフトウェアだ,コンピュータシステムだ,通信だ,と個別の性能を上げるだけじゃだめ。それらの組み合わせ全体の性能を上げるIT全体を見渡す強みが必要。融合と連携。有機体経営。どうコラボレーション、協調、共同できるか。池田さんに言わせると「感動だ」ということになる。あれするな,これするな,ではない。やっぱり同じ方向を向いて動かしていくのがすごく大事。私も入社したときは,自分の問題を自分で抱えて,先輩方は理不尽だと感じた。実際,日本のように価値観が多様化して,いろんなものがある中で,みんなの意識を同じベクトルに向かせるのは大変。強制的に脅してやっても長続きしない。そういう意味で,池田さんみたいに感動を軸にしてやっていったのはすごい。自由だけど,どこに軸をもっていればいいのか。プロジェクトXに出てきたとんかつの「あたり屋」とは,駅前にあるトンカツ屋。そんなにうまくもないが,時代としてキャベツにトンカツというのはよかったのだろう。共有化できるのは重要。そういう視点でみなさんも上なり横を向いて,その人が何を言いたいのか分かっていると,将来ある地位について引き連れていく場合重要になってくると思う。
企業のトップの方に,ウチの会社のトップが話している内容をもってきた。
ITは情報技術,ICTというのはコミュニケーションを入れている,情報通信技術のこと。90年代を振り返ると予想に近い進歩は,ハードウェア。ソフトウェアは予想に届かなかった。予想以上のものは,インターネット関連。
半導体の技術進歩の話。分子五個分くらいで配線が引ける。これから分子レベルで操作して,超微細技術が何処まで行くか。あと10年20年くらいはシリコンの技術だと思うが,世界ではその次を考え始めている。ベル研究所が全世界のトランジスタを数えたら,20万兆個あったそう。これを人口で割ると4000万個。意識せずに使っている。これが人間の生活を変えないはずはない。
ディスクは小さな大ファイル。パソコンのディスク装置は,文字で換算すると200億文字,文庫本では4万冊。町の本屋では棚に2万冊あるらしい。町の本屋2軒分をラップトップで持ち運んでいる。それの使い方を考える,自分が使いこなせば本屋2件分の知識が使えると言うこと。
光多重伝送技術では,新聞450年分を一秒で送れる。髪の毛よりも細い光ファイバーで,今まで圧縮していたりしたが,1つの光で,圧縮したりせずに送れるようになる。1.7テラで,波長の一つ一つを各家庭,各企業に割り当てることができる。一本の光に圧縮して送る技術と,圧縮せずに波長ごとコントロールして送るということを世界で研究開発されている。
情報検索の技術で,エージェント等。人間が一生かかっても読めないような量を一秒で検索できる。
ソフトウェアにはサービスをつけて付加価値を高めている。ソフト・サービス化ということで、携帯電話にはいくつか内蔵ソフトウェアがあるが,これが120万ステップ。これは,全銀協のトランザクションに匹敵している,これが携帯電話の中に入っている。A4三万ページ分になっているが,どこかが悪さしていると大変なことになっている。120万ステップだと非常に手間がかかるし,信頼性も保つ必要がある。テストケースでは7万ケースにもなる。ハードウェアを作るのも大変。小さくしたり,液晶をいれたり。だが,ソフトウェアの方が,産業としてはコストが非常にかかる。ソフトウェアエンジニアの給料等,そういうものを全て入れれば,大体一人当たり700万のコスト。給料その他含めて考えると,総計でいくらかかるのか,非常に大変な時代。
浜松にはスズキがあるが,トヨタもいいお客さま。設計なんか昔は畳の部屋でやっていたが,今はCAD。これを使うと,新車の開発期間が短くなり,車は後ろから見たデザインが大変らしいが,日本とヨーロッパとアメリカで,3つの設計部隊をネットワーク等で一緒に作業できるようになっている。
インターネット技術が多様化して,モバイルやITSなど,これまでに無いものが出てくる可能性があるが,一番大変なのはやはりソフトウェア。
物を供給する側で大変なのはソフトウェアだが,今度は利用する側からの視点。
例えばコンビニエンスストア,日本で一番成長している小売業者だが,一軒あたり30坪で3000点の商品がある。こうなると売れないものは置けない。その辺を売れ筋の情報で武装している。売れ筋をどう把握しているかと言うと,レジで,何を買ったのかということを分かるようになっている。問題は誰が,ということだが,レジのテンキーに年代と男女別というのがある。50代男性,40代男性,主婦等なっている。こういうものを集計して情報武装している。どういう人に何が売れるのかということがわかる。
1つの例で,バレンタインデーのチョコレートとホワイトデーのキャンディという話だが,バレンタインデーは男性がもらって,ホワイトデーは女性がもらう,ということだが、売れ筋をみると,高いチョコが売れるのは,当日の夕方,しかも中高年の男性が買っている。見栄を張っているということだろう。ホワイトデーのキャンディは,男性が妻に頼むから,前日にたくさん女性が買っていく。
そういう情報をどうやって集めて活用するかということが大切になる。近くで小学校が運動会だ,となれば塩気があるものを前に並べるとか,コンビニはそういうことを分析している。
アマゾンでは,推理小説を頼むと「推理小説がお好きですね」とポジティブなマーケティングをしてくる。
テキサスの小売店,これは小さなことだが,週末にオムツを買っていく20代から30代の男性が多いらしいが、一緒にビールを買っていくということに店主が気付いた。それで木曜日の夜に,紙オムツの隣にビールの棚を移動させると,皆必ず買っていくと。きっと週末に,「帰りに買ってきてくれ」と頼まれているのだろう。それで週末は,子育てを手伝いながら,ビールを飲んで,フットボールかなんか見る。
そういう小さな話だけど,マーケティングとかこういう話が,これからの時代に非常に重要な示唆がある。データをつかんで,その背後にあるものを分析したら,オムツの隣にビールの棚を動かす,それを実践している人が一番えらい。頭でわかっていても実際にやる人はあまりいない。データを分析したりして,それを実践しないといけない。ダメなら戻せばいい。これからはそうやって行かないといけない。それをスピーディにできるかどうか,そして改善ができるかどうか,そういうことが問われていくと思う。
LSIの進化で性能の曲線を書くと,いつかは限界が来ると思う。これは参考まで。
ITの今後。世界中のコンピュータが1つとして動く。繋いで見るとインターネットとかTCP/IPでつながっている。しかし,本当にコンピュータを効率よく接続しているか。例えばセキュリティとか含めて十二分に使い切っているかと言うとそうでない。これからはそこが問われる。
知識処理ということで,データベースに映像が入ったときの検索とか,そういう技術が大事。
アメリカで,IT、バイオ、ナノテクノロジーに膨大なお金が投下されている。今年アメリカの国家としての重要項目に新しい柱がたった。それは認識,センシング,これが最も大事だと。ITに関わらず,人間が認識する,これが大事。コンサートなんかで火事になると,人間は入ったところから逃げようとするらしい。そういう人間の認識をどうなっているのか,ということが研究されてきている。
長いこと半導体の技術進歩は右上がりのラインだった。ムーアの法則と呼ばれている。これが1つのリーディングエッジ,引っ張っていく技術の1つになっていた。半導体技術の進歩がITの進歩の尺度。最近ではそれとは別に,フォトニックネットワーク,光通信技術がムーアの法則よりも進歩が早くなってきている。ネットワークがどの程度送れるかということにあわせてシステムを設計するようになってきた。これに注目した方がいい。
移動通信ということでは,アナログからデジタルになり,小型化した。第三世代では国際ローミングやマルチメディア処理が可能。世界は第四世代を見ている。移動通信技術は非常に影響がある。場所を選ばないということもあるが,それで自分のいる位置を特定できるということも,非常に重要な技術だと考えている。
ブロードバンドになると,コストは1000分の1、料金は100分の1といわれている。慶応の村井先生と話したときに,IPv4では枯渇して,IPv6になると色んなものにIPがふれると言う話をした。今,衛星で場所を特定したり,あちこちにアンテナを立てたりして,非常に社会的コストがかかる。これをワイパーやタイヤなんかにセンサーをつけて,ワイパーの動きで,雨の強さがわかったり,タイヤの動きで渋滞情報や路面の情報なんかがわかる。これは凄いことであると同時に社会的コストの軽減につながる。全ての電柱にカメラを置くなんてことができないんだけど,こういうやり方だと可能になる。
ブロードバンドがもたらす変化と期待。映画タイタニック一本がFTTHでは2分40秒で遅れると,これはよくわかっているが,やっぱりツタヤにいったほうがいいんじゃないか,とそういう人間の心理。技術は馬鹿にしてはいけないが,もっと人間の心理にまで踏み込まないといけないのではないか。あらゆるところでこういう良い技術がどう使えるかということを考えて欲しい。
ブロードバンドで変わる企業や社会。企業が一番求めるは,社長のメッセージを津々浦々に伝えるということ。これは結構大事。一人一人が,会社の意図を正確に理解する必要がある。
あとはPDA。富士通製のPDAは世界で一番軽いが,これを作ってくれと言ったのは,カネボウの女性のセールスレディの部隊。こういう人達は,会社にいなくて,デパートだとか,色んな会場だとか,常に外に出ている。週に何回か会社に行ったったときに,使いたい情報をボンボンつぎ込んで,それをプレゼンテーションに反映させたいということ。電車の中からでもネットワーク経由で本社からデータを得て,午後の説明会に行くような,そういう使い方をしたいとウチの社長に直訴した。こうした発想は技術者からではあまりでてこない。
官庁自治体,電子政府ということで,こういうものを活用して効率を良くする。今のままでは,税金の分のサービスが出来ないと非常に危惧している。皆が多様化しているので,自治体がどうやってその意見をくむかということをトップは悩んでいる。行政をサービスとして捉えて,それをより効率的にやるということで,官庁でもこういう技術を使いたいと思っている。
あとは家庭,個人。色んな問題をサポートしている専門家に見せたり,同じ悩みを持っている人同士がつながったり,今までは,高齢者や障害者などは非常に孤軍奮闘していたが,そういう技術で解決できると思う。
ユビキタスということだが,何を言わんとしているかと言うと,例えばダムの上に乗っている観測機器にもIPアドレスをふって,チップを載せたりしてできるのではないか。技術的にはそういうものをネットワークに接続して活用する時代になっている。
そうなるとネットワークの構成はどうなるのか。各家庭からだと,最初の出口はどうするか。それは無線にすればいいとか,そこからバックボーンに行くまではどうしたらいいか,さらに背骨にあたるバックボーンはどうしたらいいか,これは日々刻々と変わっているので,インターネットを活用したりして見られるようになっている。通信事業者も情報を開示してきているので,今使える最新の技術を加味して,ネットワークを設計し,今使える機器を最適配置すると,そういうことができる技術者は重宝される。
技術はかなり凄いところまで来ていると考えてもらっていい。特にハードウェア技術はとても進歩している。ところが利用技術はこれから。そこではネットワーク技術が大切になってくる。それをどうするかというところ。これは一人で考えることではないが,大切。
ユビキタスとは、元々ラテン語で、「遍在する」という意味。「いつでも何処でも」だが,「何のために」が無い。ここが大事、本質の部分。堀田先生と一緒に仕事をしたが,そういう本質的な部分を外さない方。技術が目的ではないので「何をするのか」ということを考えないといけない。日本のIT産業,あるいは産業界全体がそういうところにあるのでないか。手段を目的にすると一番楽だが,特にSEは研究者ではないので,社会にどうやって適応させるのか,そういうことをしっかりやらないといけない。研究者はいいものを作ればいいが,SEはそれを社会に定着させないと評価されない。いつでも,何を目的にするのか,例えば高齢者の何を助けるのか,それは社会的にどういう意味があるのか,そういうことを考えないといけない。戦後,産業界全体がとにかく所得を倍増させようとか,そういう発想で組織や企業を作っていった。そういうことが企業の目的になってしまった。株式会社という制度は,ある目的で違う能力を持った人たちが集まって,それを実現するという精神があったのに,利益利益で,それは手段だとは思うが,それが行き過ぎて変なことになってきている。そもそも目的が何だったのか,ということを振り返る機会を持って欲しい。特にSEは社会との接点が多いから,議論してみるのもいいと思う。
 |
■午後の部
第3章IT政策の動向。e-Japanについて。規制緩和をどう考えていくか。国際的なルールメイキングがどんなところで,どんな風に起きているか。又、ITの活用,人材について。
まず政府の取り組みで,これが全体の構成の図。IT基本法に基づいて2001年の1月にe-Japan戦略が策定され、それに基づき、e-Japan重点計画が立てられた。それを毎年見直す意味でe-Japan重点計画-2002がある。省庁横断的に,小泉首相を本部長にして,閣僚と民間あるいは大学関連の人9名のIT本部がある。その中に私たちの社長の秋草も入っている。こういう形での法律は今まで日本では作られたことがない。それを戦略という言葉でプロモートしたこともない。大変画期的。なおかつこれを毎年見直す。ふつう法律は成立させたら10年,20年の間は変えない。
インフラ整備として、5年以内に3000万世帯に高速インターネットを普及させる。6000万世帯あるうちで3000万世帯をブロードバンドに。更に、1000万世帯に超高速インターネットを2005年までに実現するということを,国がコミットした。当然ながら,超高速インターネットだと,安価に常時接続。「安価に」というのは言うはやすく,それを各家庭にひくのはとても大変なこと。「常時接続」というのも大変。光ファイバーをひきたいよ,という人が出てきたらすぐに引けるようになっている。
インフラの整備と競争を促進させる。NTTと電力会社のインフラ整備を競争させたり,CATVと日本テレコムを競争させたり,競争によって安価になった。今後はサポートを充実させていくことが大事。産業界にすると厳しいことだが,日本を付加価値の高い国にしていかないと,国として成り立っていかない。危機感の裏返し。
e-Japan重点計画。220の具体的施策と実施全閣僚が参加して各省庁がパフォーマンス評価をしている。e-Japan重点計画2002では、318の具体的施策をすすめたり,出来ることをどんどん前倒しして加速していく。
どんな構成になっているか。縦に5つの柱、重点政策をたてている。(1)世界最高水準の高度情報ネットワーク形成,(2)教育・学習の振興と人材育成,(3)eコマースといわれるような電子商取引の推進,(4)行政・公共分野の情報化,(5)高度情報通信ネットワークの安全性・信頼性確保の5つ。
それをつなぐ横の柱として5つある。(1)研究開発推進,(2)地域による格差,(3)はお年寄りがPCを使えたりするようにデジタルデバイドの是正。(4)雇用問題。物流とか,卸といった従来の産業の階層構造をネットワークがスキップしてしまう。当然のことながら,その途中の段階にあった業種・産業が消えていくことがあり得る。ネットワークの利便性だけでなくある意味痛みを伴う。インターネットはつなげた瞬間に世界がつながる。(5)として、どのように国際協調するか、こうした政策をすすめる上での国民の理解を深める措置がある。
重点政策の(1)について。政策を考えるときに現状評価を徹底して調べる。それまでに実施した施策,足りない部分,強化する部分を書く。ネットワークの今後の施策のところで,たとえば「電波資源の再配分方策」のところ。携帯電話,モバイルネットワークのために,今まで使っていた人にいったんどいてもらう。道路を作るときにそこに住んでいる人にはどいてもらう。そのときの経済的不利益をどう補填するのか。そこで競争させて,周波数を競売にかける。欧米ではもうやっている。国が売りに出して1億円,100億円,1兆円というような額で周波数を売る。これは、市場のオークションで国の限られた電波を最大限に使う仕組み。民間企業は多額で電波を買う。その分をユーザーの負担になるので,場合によってはマーケットが死んで会社がつぶれることもある。電波資源の再配分方策というのは悩ましい問題。
既存設備を活用したネットワークの形成。地方自治体は,地域の産業を活性化させたい。そのためにはネットワークを自治体の税金で作ってしまおう,というところがある。そのネットワークをお金を出す民間に開放しようというところもある。たとえば,下水道の中に光ファイバーは簡単に通せる。そうして地域のネットワークをどうするか。
自由かつ公正な競争環境の整備の促進。NTT,KDDIとか,事業者は全部この法律にもとづいて許可・認可がされている。ここをより自由にするにはどうするか。たとえば,明日から通信産業業界に参入する人をどう迎え入れるか。
ブロードバンド時代に向けた研究開発,国際インターネット網の整備,etc...
重点政策分野の(2)は、学校教育の情報化。小学校から情報に関する基礎的な学習,学校インターネットの整備。ところが,大学では整備できても,地方の学校では3つしか電話回線がないというようなところがある。各教室にネットワークを引かなければならない。子どもがある時だけパソコン室に出かけていって使うというのではだめ。紙や鉛筆や消しゴムのように使うようにするには各教室に置く必要がある。そのために校内LANが必要。しかし校内LANでインターネットに接続すると全く知らない大人が居る。学校内でどう安全にインターネットを利用するか。専門家の養成など必要。
重点政策の(3)は、電子商取引の促進。たとえば,規制の見直しとして,株主総会の見直し。株主総会をインターネットで出来るようにしたらどうなるか。又、海外旅行したいとしてチケットを取るとする。ちょっと前までチケット販売は商法上,対面でないと買えなかった。インターネットで買うにしても最後は対面で受け取る必要があった。そこを便利にするためにどうやったら可能になるか。技術的には可能でも,成りすましたり,買ったけれども支払わない連中にどう対策するか。同様に,何かしようとするときに,からみあった糸を解いていくような作業が必要。
重点政策の(4)は、行政の情報化および公共分野における情報通信技術の活用の推進。いろんな地方に交付税として何十兆円か渡している。それに地方で受け取る税金などから地方行政は成り立っている。税金の2倍くらい社会保障や社会保険のお金が必要。だんだん,それだけのお金を集めていくのはつらくなっていく。そのときにITを活用できないか。ひとつの市町村では収入と支出があわせられないので市町村合併を行う。その場合に図書館が20カ所になったときに,インターネット経由で宅配便とあわせて本を借りられるシステムなどが考えられる。税金を払った人に対するサービスとして何か新しいことができないか。
重点政策の(5)は、安全性・信頼性。去年の9月11日のテロ以降,アメリカはすごいスピードで大統領直轄のサイバーテロ対策チームを作った。そのときキーになるのは,テロが起きる前に水面下のネットワーク利用が活発になっているので,そこに対してどういう対抗措置を練るか。自由の国といっても悪用しようとする人も高い技術でせまってくる。日本は意外とのんきに進めている。
横断的課題への取り組み。デバイドの問題,バリアフリーの問題。高信頼性のこと。国際的な協調・貢献としてアジア地域内の高速インターネットとどう接続していくか。
e-Japanの広がり。欧米ではNPOが盛ん。全部が全部収益をターゲットにした企業でもないし,全部が全部上に任せることでもない。アメリカの開拓精神として,中間で出来ることはどんどんやっていく。企業のIT投資を拡大し,新しい産業を創出していく。
富士通のe-Japanビジネス。公共施設の利活用をネットワークで最適化できるか。
教育,学習支援の分野。学校の先生にも校務がたくさんあるが,それをうまくサポートする。
行政の窓口でもたくさん並ぶところがある。月末には,不動産業者や建設業者が,工事等の関係で並んでいる。これがお役所仕事でやられると,ビジネスの面では非常に不利益が生じる。そこで,窓口をどう効率的にやるか,そういうことを行政も考えている。
医療介護分野。今は税金が高いといわれているが,税金以上に,医療福祉にかかるお金はとても増えてきている。高齢化は確実にやってくる。介護される人が増えて費用が増えてきている。こういう問題にたいして,電子カルテ,カルテは今までお医者さんから門外不出だったが,それが各病院で交換できるようにする。また,毎日病院にこなくてもいいということになれば,支出を抑えられる。病院経営も合理化できるところがあるかもしれないし,医療ミスの問題も,今一部の病院で実験しているが,患者さんにバーコードを持ってもらって,薬の側にもバーコードを振って,それを突き合わせることでミスを減らす。看護婦などの負担を減らす。
環境という問題,廃棄物など。例えばパソコン。最新のパソコンはラックの外側の部分をとうもろこしから作ったりして,土に返るようにしたり、製品のラッピングを紙に戻したり,緩衝材に発泡スチロールをやめたりして,環境への負荷を減らしている。環境の問題も,先の人口の問題と同じで必ず社会にふってかかる問題。
業種でいうと,製造,金融,流通,小売,情報を対象とする。こういうところでどんなことに適用できるかを考えるのも我々の仕事。
規制改革推進三カ年計画。つまり,仕組みを変えていこうということ。いくつか柱があるが,インフラの整備の面では,線路敷設の円滑化ということがある。ネットワークを引こうと思って道路を掘るときには役所の許可が必要。河川の下に線を通そうと思ったときは別の役所に許可を出す。こういう認可は確かに必要だけど,どういうルールでやるべきかということは考える必要がある。
電波の周波数割り当てを見直すとき,既存の人をどかさなくてはいけないが,ここの補償をどうするか。いま,無線LANがスターバックスにもあるが,コーヒー屋であるけれども,ある意味では電気通信事業と言えるかもしれない。ガソリンスタンドで,車の状態を無線で判断するような仕組みがあったとしたら,そこの区切りはどうするのか,免許無しでやらせた方がいいかもしれない。
電力線搬送。一番各家庭に普及しているのは電線。その線を情報通信にも使おうという話があるが,その際,干渉のことなど色んな影響を考えないといけない。
インフラ整備の具体的な動きの例としては例えば東京電力が動いている。FTTHのサービス。あるいは,電力会社同士で横のネットワークを使う等。電力会社は光ファイバーをたくさん持っているし,経済的にも非常に強固なので,そこに進出しようとしている。地方自治体でも自前のネットワークを整備しようという動きがある。
あらたな競争政策として,非対称規制の導入がある。競争といっても,NTTは昔,電電公社として,電話債権を活用して電話を整備した。それが民間企業になりました,と言っても,昔に公共的な資産として整備したものがあるわけだから,民間のゼロから始めた会社とは違った規制のかけ方をすると。全体的には規制を緩和する方向にある。事業区分のことで,電気通信事業者には一種と二種がある。一種というのは交換機などの設備をもっている事業者のこと。二種はそれを借り受けてビジネスをしている会社のこと。うちで言えばニフティがあるが,この一種二種の区分を無くそうとしている。プロバイダなんかには不利になるのではないかと心配する人がいる。例えば設備を持っている側が貸し出しを拒否したらどうなるか,なんて問題がある。
通信/放送の融合。通信と放送の法律は別々にあった。これからデジタル放送時代になると何にも違わないので,法律は一緒にした方がいいと言う話。コンテンツやプラットフォームとか,水平的に捉えようという話があるが,各事業者で意見が割れていて難しい。
電子商取引,対面販売の義務付けを緩和したり,薬事法などを改正したり,書類保存義務も,紙ベースではなくて,電子的にできたらどうだろうか等。株主総会の議決権も電子的に行えたらどうか等,変えなければいけないところは多い。
不当廉売という法律の規制がある。過剰なおまけや景品をつけるようなもの。それがネット上で景品を出しているところはどうか,など。
個人情報の保護はどうしたらいいだろうか。これは法律論ではなくて,何のために,ということを考えないととても難しい話になってしまう。ロサンゼルス地震以降,ボランティアがマンションなどの家族構成を知りたいという話があったが,プライバシーの関係で教えたくない,と言う人もいると。しかし,非常時に不利益があるかもしれないということを覚悟してくださいね,となる。そこで一人一人に確認していく,そういうことが必要になってきている。
ISOCという学会があって,IETFという,ここがTCP/IPを作ったところだが,これは全世界の技術者のボランティア団体。ICANNというのもあるが,ここはドメインの管理を行っている。これは全部アメリカの団体で,こういうところはアメリカが抑えている。ICANNの理事19人のうち,5人を5大陸から選挙で出すという話があって,ウチの当時のワシントン事務所の人間が出ていて,私は選挙参謀をやっていたが,非常に大変だった。
IETFの総会を横浜でやったとき,インターネットの育ての親みたいな人々が来るわけだが,慶応の村井先生曰く,そういう人間は5秒でもインターネット接続ができないと窒息すると,途切れたら富士通はえらい目にあうと言われて,非常に苦労した。その会議で,私なんかは全然議論に参加できないが,東南アジアの技術者なんかは片言の英語でもバンバン議論していく。そしてそこで色んなことが決まっていく。人材の話にもつながるが,大変なことだと思った。
こういうところの趣旨は,そういうルールを決める際の議論に参加しない組織は後追いだから不利益を生じても仕方ないと,そういうことである。日本以外の国はそれを理解して一生懸命参加しているが,日本というのは,これは特性かもしれないが,「ルールはお上から」のような意識が抜けない。アメリカではルールは自分達で作ると言う精神がとても旺盛。日本人の奥ゆかしさは通用しない。でも,じゃあ,参加者が大したこと言っているかと言うとそうでもない。だから自分の意見をどうやって伝えるか,あるいはディベートとか,各国とも若い人に一生懸命教えている。
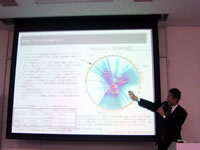 |
市町村合併。市町村の数が三分の一になる。市長さんは大変。会社でいえば社長。コンピュータシステムや住民に対する公平な担保など大変。
独立行政法人ということで,大学なんかも法人格を持たせて独立させるという話があるが,こっちの大学でも学長さんなんかは生き残りを考えているはず。そういうなかで大学が評価される点は2点。一つは教育。ちゃんと優秀な学生を輩出しているかということ,それは評価される。もう一つは研究。そういう意味では卒業しても皆さんは後輩への責任を背負っていると思った方がいい。
教育の情報化。コンピュータを使って何ができるかということを子どもにもっと伝えた方がいいと思った。ただ,富士通がそれを急に言い出して,製品を売りたいだけだろうと言われるとしゃくなので,参加型のものにした。これがインターネット博覧会でやったFATHeRS。技術的なことを求めるのではなく,子供たちが新しいものを創造したりすることの楽しさと,コミュニケーションの大切さを知って欲しいという観点でやった。それを堀田先生に相談して,全国で300人くらいの先生をアレンジしてもらって,参加してもらった。1つ例を挙げると,秋田の小中学校で5人みたいな小さな分校と,筑波の1000人規模の学校とで,お互いのホームページを作りなさいということをした。そうすると,お互いの学校を紹介することから始めると,環境が驚くほど違う。そこで一生懸命コミュニケーションして,子どもたちがとても立派なホームページを作った。最終的には文部大臣賞か何かをそのチームがもらったと思う。
総合的な学習の時間が始まって,総合的な学習の時間というのは,自由にやれということだが,逆に何をやっていいかわからないので,その有効な利用に関しても役に立ったと思う。給食の写真を投稿してもらって地域の違いを知ったり,こんなパソコンがあったらいいなという作品を書いてもらったりした。そういう人たちを元気付けようと思ってパソコンを持っていったらとても喜んでもらえたりしたが,中学に入れば環境が変わってパソコンが無いとか,高校入試のことを考えるとパソコンをいじっている場合じゃないとか,そういうことがあって,うちの会長が入試がいかんとか,学校の成績からだけで社員を取るのは止めようという話になっている。企業にしたって安定なんて何もない,いい学校いい会社みたいなモデルはとっくに崩壊している。今色んなことを変えようとしている。
これはパソコン少年を要求しているわけではない。ただ,パソコンも使えますよ,コミュニケーションも出来ますよ,ということに価値を見出して欲しい。
FATHeRSという名前は私が付けたが,fatherというのは父親という意味の他に、創始者という意味もある。東証がMothersというベンチャー向けの取引所を作ったが,そこの人たちに,Mothersで集めたお金をFATHeRSに投資しませんか,と言った。もちろん儲けが出るわけではないが,こういうところに集まる人たちに対して,実費くらい出ないのは,この豊かな日本でおかしいと思ったわけである。
住民基本台帳ネットワーク。今年の8月にベースになるインフラ,我々はバックヤードと呼んでいるが,それができあがった。来年の8月から,ICカードをそれぞれの住民の方に配って,ICカードを持っている方には場所が違うところからでも住民票が取れる。免許を取るといった作業はそう頻繁にあることではない。そうすると一般の社会に出ている人にとってどのようなICカードが便利かを実験的に調べている。たとえば札幌では,交通機関に乗れるようにカードを使えないか。高齢者のサポートや証明,あるいは商売に使う。銀行決済にICカードに埋め込めないか。コンピュータの歴史ではダウンサイジングが出てきて,クライアント,サーバー型,インターネットによってそれらが結ばれてさらにユビキタスということで簡単に携帯できる装置。家電メーカーさんはIPv6チップを入れて,何が冷蔵庫に入っているか携帯で調べられて,帰宅する1時間前に冷蔵庫をぐっと冷やすか,とか。社会的価値はさておき,そういうことができるようになる。
私がもっている社員のIDカードには,私の権限が入っている。カードの中にメモリもCPUも入れられる。究極のダウンサイジングした情報機器ということになる。もちろんカードの形にしなくても,チップをいろんな場所に埋め込める。たとえば,荷物の積み卸しや,車に何が入っているかは,いちいちバーコードや目視で確かめていた。それがトラックに入ったと同時にカウントできる。病院であればベッド,個人の患者と,薬に同じチップが入っていて,正しいかどうかチェックできる。住民基本台帳もどのように国民のコンセンサスを得ながらやっていくか。チップ自体は書き換え自由なので,何を入れるか選択できる。
市民コールセンター業務支援システムはいろんな自治体で出てきている。自治体のトップは選挙によって選ばれる。よって住民が何を求めているかを知りたがっているが,現在の役所のシステムではそうした声がトップには伝わらない。このシステムはコールセンターを設け,市民の声を集めて,データベースに集めていく。さらにそこにナレッジな検索エンジンを入れて,介護保険の施策をやろうというときに,データベースにある期待の声を分析できたりする。
皆さんがSEとなった場合,あるいはSEでなくても,全部が全部コンピュータを導入して,データベースを管理するというのは大変。それをアウトソーシングしていこう,外部のサービスを使いながら本業をやっていくという動き。そこには堅牢な設備が必要。我が社では、館林には堅牢なデータベースシステムがある。企業でも役所でも不良資産というか,ネットワークは使えるためにあればいいので設備まで持たない。
システムエンジニアの人は全部の専門家になれなくてもいいけど,社会に対する好奇心がないとできない。全部は解決できなくても,社会のつながり,風が吹けば桶屋がもうかるじゃないけれど,何がどうなればどこに影響するのかを知っておく。
総合電子カルテの話。ネットワークをフルに活用した病院。PFI(Private Financial Integration)を活用し、国や患者からお金をもらうのではなく,民間の投資家をつのって病院を経営する。また丸の内の丸ビルは三菱商事が作ったが、そのときは三菱商事が外から資金を集めて作るのと同時に,フロアごとを債権化して売った。そうすると,そこに投資した人は「あのビルはオレが投資して作ったんだ」と思うし,投資されたお店が頑張れば配当になる。新しい資金調達手段が出てきている。
世の中の関係やつながりをデジタル技術でこういう風にできるんじゃないか,ということはポイント。マッキンゼー社にはアメリカの優秀な学生がこぞって入社しようとする。それは世の中のいろんな仕事に関われるから。それによって別の仕事に移ってもやっていける。キャリアパスの積み上げに役立つ。IT技術を軸にしていろんなことを考えてみては,と思う。
企業に対するIT進展のインパクト。個別のビジネスだけでなく,産業を再構築していく。どうすればスピードがあがるか。企業の競争の原点,利益の原点は設備でもお金でもなくてスピードだ,と言われている。スピードをあげることがお客さんから対価をいただける。値段が高くてもスピードが速ければ競争に勝てる。
ITのインパクトを受けて,先進企業になろうと思うんだけど,リスクをさけてじっとして台風がすぎれば,と思っている企業がある。その結果、変化しないというリスクを負うことで衰退する。前に進んでもうまくいく保証はないんだけど,変化しなければ衰退する。
新たなサービスとしてASPサービス。着メロサービスに近いと思っている。工場で使うCADというのがある。これをそれぞれのパッケージを買ってきて導入すると,管理がものすごく大変。必要な分だけをセンターからダウンロードした方が,スピードとコストが半減される。関連会社も含めて2000事業所でやったが,具体的な数字でそういうのが出てきている。
アプリケーション・ブレークスルー。CPUやHDDが無限に使えるとしたら,世の中のこういうことが困っているとか,使い勝手を考えてみたら,ということ。新しいことを考えていいと言われても,何を基準に考えていいか分からない。そのとき,技術はいくらでも,リソースはいくらでも使えるとしたら,何か新しいことができるのはないか。発想の転換をして考えてみる。思いつきだけでなく,社会や企業や個人が求めているものをキャッチする。ニーズの大事なことは困っているところを見ると一番よいそうだ。
アジア関係のこと。通信のハブ。海底ケーブルを含め,いろんなのが出てきている。ハブはシンガポールに集中している。そうなるとシンガポールにどんどん日本の大企業がアジアのネットワークセンターを作ろうとする。中国も市場が大きいので出て行っている。上海,北京にどんどん出て行く。それによって日本が空洞化する。拠点が全部うつってしまうと,就職するときは北京に行って,北京の会社で就職しなければいけなくなるという事態も起こりうる。仕事が外に移ると,その分野の研究や蓄積がなくなる。
それを防ぐために日本にネットワークのハブをなんとかもって来れないか。ハブとスポーク。ハブをそこに置くのは,ハブを置く場所に魅力があるから。流通や税制優遇,研究者の誘致など。これができないとネットワークの最新技術をシンガポールに持っていくようになる。産業だけでなく科学技術もどんどん流出していってしまう。
私は情報と通信の一緒になったハブを日本に誘致したいと思う。研究者が居る,大学がある,通信コストも安くできる。日本国に入ってきたら,日本のバックヤード,テロやその他の問題に対してサポートできますよ,ということを日本が言えれば日本の魅力になる。中国にハブを置きたい会社は居るけれど,高度な技術をもった人,ソフトウェアエンジニアなどがまだいない。ものすごい勢いで人材養成しているけれど,まだまだ日本に居る。e-Japanで太い回線でつながれば,プロが居るところは東京に集中しなくても注文に応えることができる。
国際的情報流通の現状と方向。アジアと欧州は線が細い。日本からのデータははアメリカ経由でヨーロッパに行く,アメリカ経由でシンガポールに行く,というようになっている。インターネットの仕組みを考えたアメリカの作戦。アメリカを中心にして情報通信システムをグリップしていこうという戦略的な動きがある。私が心配しているのは,アジアの中で日本がそれなりの役割を担わないと,食料も自給していないし,外貨を稼がないと観光名所だけになってしまう。
アジア太平洋地域における海底ケーブルは、日本にも来ているが,日本が必ずしも情報通信のハブになっているわけではない。この辺のラインを魅力ある日本にして,日本がハブになるように出来ないかなと。そういう動きも海外ではどんどん起きている。
ご存じのようにブロードバンドは韓国が日本を抜いている。韓国の役人はカードで買い物をするように義務づけられている。カードを使うということは情報ネットワークを使うということで、国防の意味もこめて,韓国が一番をいっている。
インターネットの普及率。台湾は,日本が2005年までに世界一になりたいといったけど,それを2008年に追い抜くという勢いでやっている。台湾がすごいと思うのは,危機意識が強いということ。緊迫感がある。国が中国に取り込まれる可能性もある中で,国民全体の付加価値を高めて,どういう国のあり方になったとしても国民が生きていけるようにという危機意識がものすごく強い。ITはラップトップひとつあればどこでも活躍できる。
富士通の宣伝。TRIOLE。どこにシステムがあっても,どこにサーバーがあってもよくなる。情報システムは電力のようになっていくのかな,と思う。企業の競争であったり,国の競争みたいなものは,好き・嫌いを言ってられない。一番のキーになるのは人材である。
サラリーマンとして,社会の先輩としてのアドバイス。一つ目は、求められる人材は,問題が出て,その解答を作る人より,問題を自分で考える人がほしいということ。二つ目は,自分で解決策を考えて実践できる人。堀田先生が言われたこととして,実践力は非常に必要。IETFでも,言葉が通じなくても実践したら通る。それが標準になる。評論も大事なことが,実践すること。三つ目は,人の話をしっかり聞くという能力。これは訓練によって出来る。将来のリーダーは人の話を聞くだけでなく,勇気を与えること。勇気を与える人のところに仲間が必ず来る。仲間がいないとこれからの仕事は出来ないから。人の話を聞くこと,仲間に対して話をして勇気を与えること。四つ目は,ITと流暢じゃなくてもいいから英語。しゃべりたい,伝えたいという思いを持つことが大事。ITもプロでなくていいから,ITをおそれないで使う。道具としてのITと英語を厭わない。
社会に出て戦う材料は,頭で勝負することができる。その次はハートで勝負することができる。気持ちで,志で。頭でもハートでも勝てなくても胆力がある。本当に大事だと思ったら胆力,腹で勝負する。それでもだめなら粘り腰。腰でもだめだったらフットワーク。そういう意味で,人間の身体といっても5つくらい部位があるんだから,社会は一つだけ求めるんじゃないから,バランスよくいろんなものを使っていかれたらいいと思う。
もう一点。スタートするときに「出来ないだろう」と思うのはやめたほうがいい。出来るだろう,と思わないと思考が止まってしまう。欧米人はだいたい「できるだろう」と思う。マーフィーの法則で,出来ないなと思ったら出来ない。アメリカのマーケティングを勉強している人の間では有名な法則。だめだと思ったら,だめになる確率は高くなる。出来ると思って前向きにやっていると,勝利の女神がたまに微笑んでくれるらしい。e-Japanとかいろいろ言ったが,出来ないと思ったらだめ。
ご静聴ありがとうございました。
■質疑応答
森下
池田さんの話はひとりの天才がバンと進める話。行政なんかと仕事をすると集団でやりあっていく。どっちが有効に機能するか?
高橋
これだけの巨大な技術を利用する,適用するというのは,池田さんが居ればという時代じゃない。池田さんはテクノロジーを追究した。それに対して利用技術というときにはポイントゲッターを見つけてというより,いろんな人たちを参加させて,参加型でどうやって付加価値を高めていくのかという事の方が重要。利用はその後運用でつながってくる。社会システムになると,社会のコンセンサスを得るのが必要。仲間をどういうふうに増やしていくか。技術を適用していくところから仲間をひきこんでいく。IETFもそうだし,Linuxなども技術もそうなってきている。利用技術のところではどうコーディネーションするか,ひとりにおんぶにだっこするのではなく意見をどうくみ上げるかである。
このページは,2002年に静岡大学情報学部において行われた集中講義・情報学特別講義IIIの記録です。著作権は講師(発言者)に所属します。