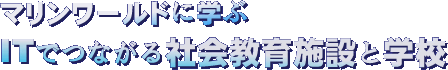
サメ空輸作戦の裏話
さっきの休憩時間中に面白い話をしました。オーストラリアから飛行機でサメを運んだ話で,飛行機にはクルーが3人乗ってる。それで僕も飛んでる飛行機の操縦席に座らせてもらった。そこで操縦士に,「お前を呼んだのにはわけがあって,俺は日本に飛ぶのは初めてだから,日本の福岡空港はどっちか教えてくれ」と赤道を過ぎたあたりで言われた。かなりびっくりしました。もちろん冗談だと思いますけど。
話に戻ります。
マリンワールド海の中道の教育プログラム
水族館は教育施設だから,職員は教育的な面も知らないといけない。
解説によって情報を伝えることも教育と考えていい。展示で情報を伝える。設備で,レクチャーホールがあって教育するとかいうことも考えられる。人の活動も重要。私の今日の講義もそれに当たります。学校への教育支援もひとつの活動
もうちょっと詳しくすると,学年に合わせていくつもの教育プログラムを持っています。ワークシートがあったり,講話したり,遠隔授業したり,離れたところに生物や標本を持って行って移動水族館したり。大学・専門学校になると,だんだん高度になっていって,博物館実習をしたり,卒論や修論の指導もします。します。一般の飼育実習もあるし,講師派遣もあるし,ボランティア活動もある。市の教育委員会が持っている宿泊施設があって,そこに来る人向けの講話や実習などのプログラムも持っている。
こういう教育プログラムをまとめた冊子があって,メニューを選んで申し込んでもらうようになっている。
こうやって教育活動を当たり前にやっているように見えるけど,ここになるまで10年かかった。説明に行っても,そこに資料置いておいてと言われて説明もさせてもらえなかったり,説明させてもらっても3分しか時間をもらえなかったり。そういう状況が10年続いた。ようやくここへきて色んな学校から引き合いがあって,言い方は悪いかもしれないけど,売れるようになったわけです。
総合的な学習の時間や週五日制の導入とか,社会の変化と,僕らの10年の努力が実を結びつつあるのが今の状況。
学校はウィークデーに多く来ます。もっと言うと,水曜や週末に集中する。ほぼ毎日なんかのプログラムをやっているような感じで,一日に複数のプログラムをやっていることもあります。そういう状況。内部の人間同士で,やっとここまできたね,と言っています。
もちろん,一朝一夕で学校とこういう関係になれたわけでなくて,ああでもないこうでもないと考えたり,ここにいる堀田先生に指導してもらったおかげでもあります。
ネットワーク授業,これは内部でそう呼んでいますが,いわゆる遠隔授業は,そういった教育プログラムの中のひとつ。平成10年から始めたが,全国の博物館で遠隔授業できたのは10館くらい。NTTのこねっとプランというのが当時あってやりました。で,平成10・11年でやったんだけど全国には広がらなかった。それで,文科省からお金をもらって,九州内の5つの館ができるように,システム構築とか支援をしてきた。この2年間で6000万円くらいの予算を使いましたが,もちろん,このお金は国から出してもらって支援してもらってできた。そのお金が出たのもさっき言ったような制度の変化があって,それにマリンワールドが答え続けてきたから,予算をつけてもらってできるようになったんじゃないかなと思います。
ネットワーク教室
http://www.kmnet.gr.jp/
この事業では遠隔授業やっただけじゃなくて,各博物館がもっているコンテンツをデジタル化してCDにプレスして配布した。先生が教材を検索して,写真・動画・ワークシートなんかを使えるようにしている。ディスカバリーボックスと言うのは,映像はあくまでもバーチャルだからということで,事前にサメの歯を送って触ってもらったりする実験観察キット。
遠隔授業と言うのは,学校ではイベント的な使い方しかしない。その日だけ「あー楽しかった」,となっちゃう。事前学習や事後学習がセットになって,プログラムになった学習じゃない,だからパッケージにして,教師用指導書とかも一緒にして配布したら,現場で使ってもらって教育的成果がだせるものになるだろうという風になった。そういう2年間の取り組みが本になっている。是非見てください。
そういった遠隔授業をやっていくうえで,Webページで受け付けをしたり,成果を発表したりしています。CDは6100枚プレスして,九州内の全ての学校に配布した。
 ディスカバリーボックス |
ディスカバリーボックスの実例。これはサメの歯が入っているもの。ほかに,30メートルのクジラが入っている箱というのがある。箱を開けると,30メートルのロープがあって,そこに目とか口とか尾びれとか書いた札が下がっていて,グランドで広げられるようになっている。さらに先生用のシートには,ラインの引き方が書いてあって,ラインマーカーで線を引くとグラウンドにクジラができるわけです。ロープ一本でクジラを学校に持っていくことができる。実際の授業では,ロープのほかに2メートルくらいのイルカの剥製も持って行った。何の教科で使ったか分かりますか?これは算数の授業で使った。イルカはクジラの何倍ですか,という比べる数と言う授業。教科書ではさらっと書いてあるけど,子どもは実感が無い。実際に比べると,どの位の違いかと言うことを未を持って感じられる。算数の授業でもそういうことができる。もちろんこの授業の前には,遠隔授業をしている。そういうことがあるから意味がある。
海辺のゴミ拾いをするような授業作りもしている。
子どもと地域の水辺の生き物をデジカメで取って図鑑作りをする授業。海岸のゴミを調べてどこから来ているかと言う授業もやる。
水族館で水の生き物を見るだけじゃなくて,そこで働く人の仕事を知ることで,さっきのクジラを救う話とか,環境とか生物とか,そういうことを学ぶことができる。
学校に提供する情報はデジタル化して,CDとかWebとか,デジタルコンテンツにして提供して,しょっちゅう水族館に来なくても情報が得られるようにしている。
PDAの授業もありました。生き物の情報をPDAを新聞記者の手帳と見なして,生き物の情報を探して新聞作りをしている。今まではアナログベースでしていた。今回はデジタル的な機械を使ってやった。子どもはこういうものを使って取材し,それをHTMLデータでで渡して,学校でさらに編集したりできる。
事前に入力練習をしたり,新聞作りの授業があったり,新聞記者の出張授業があったり,そういう意識を高めたりして,それでPDAがある。ポンと渡すんじゃなくて,情報を得てゆく前の過程がある。
環境を調べてもらう。調べるだけじゃ学芸員の仕事ではない。デジタルばっかりじゃない。川と干潟と海がある学校の子どもをジュニアキュレーターとして任命して,環境を調べてもらう。調べただけじゃ学芸員の仕事じゃない。人に伝えるために,子ども達が企画会議をしたりしている。中にはパソコンで作る人もいたり,マジックで書く子どももいた。川・干潟・海という違う環境の学校が,企画制作プレゼンまで,自分達でやる。これも情報教育,パソコン使うだけが情報教育じゃない。自分達が調べたことをまとめて発表するまでの過程がある。ちゃんと情報教育の要素が練りこまれている。子どもが解説員になってお客さんに開設する。こういった場所を貸したり,アドバイスするのもうちの仕事のひとつ。
展示のひとつである解説を充実させる
水族館の商品は,展示だけじゃない,ショーだけじゃない,解説も重要な展示のひとつ。だから解説は読めればいいとかそういうレベルでは商品にならない,わかりやすく伝わる努力が去れないといけない。
文字にしたって,読んでもらえる文字の量とか,読みやすいフォントとか。映像にしたって,画質とか,シナリオとか,全てにわたってそういう工夫がなされないといけない。
もちろん人自身も重要な展示のひとつだから,職員はそういう意識でないといけない。
文字情報で伝えるテクニックがいろいろある。新聞は文字情報としては読んでもらえるテクニックが凝縮している。忙しい人は見出しを拾って読む。興味があれば数行読む。そういうテクニックが水族館にもあって,展示の表題とか,重要なことが箇条書きになっていて,お客さんが全部読めなくても,さっと情報が伝わるようにしている。
水族館はレストラン。レストランといったって,いけす料理の話じゃない。人はみんな,どんなレストランが良いかと言うと,美味しいのがいい,安いのがいい,清潔で雰囲気がいいのがいい。接客で気持ちがいいところがいい。これと同じことが水族館にも言える。美しく見やすい展示と情報があったほうがいい。展示と施設に見合った料金であるといい。静かで清潔なほうがいい。職員は親切に対応してもらえると気持ちがいい。レストランと同じことが水族館にも言える。じゃあ水族館のコックは誰か,それは学芸員。料理をちゃんと食べてもらっているか,楽しんでもらっているか,残していないか,そういうことを把握しないといけない。だから学芸員は現場に出てお客さんがどういう風にしているかをちゃんと見ていないといけない。もちろんコックだけじゃレストランはできないので,営業の人間がウェイター・ウェイトレスになって,サービス業に徹して,気持ちよく過ごしてもらえるようにしないといけない。
学校の先生との関係では同等じゃないといけない。日本の学芸員のなかにはふんぞり返っている人もいるけど,子どもの学びのために同じ意識レベルじゃないとやっていけない。学芸員には専門技術や知識や本物がいる。学校には教えることの専門家がいる。そこはお互い尊重しあって協力する。
博学連携は新しいビジネスになる。そのためには学校のニーズを掴んで,質の高い教材なんかを提供していく。だから博物館は教育産業であっていいと思います。
質疑
− 今,高田さんは副館長と言うことはどういう立場なんでしょうか
高田
あるときは電話番,あるときは学校に行くこともある。あるときは飼育番でもある。さっきも言ったように水族館の人間は色んな仕事をしている。ただ,副館長としては全てに責任を持つし,お金の計算が出来ないといけない。そういうお金のことも含めて全てに責任を持たないといけない。
堀田
日本に水族館は何館ありますか。
動物間水族館協会に登録されているだけで,約70館あります。静岡には4館ある。静岡県は水族館王国。4つもあるのは和歌山と静岡しかない。
今日は,浜名湖の施設に行ってきた。水族館ではないが,浜名湖にはウォットと海湖館というのもある。それは動物館水族館協会には登録されていないわけですから,そういうのも含めると100とかになるでしょうね。
堀田
そのうちで,公的なものはどれくらいありますか?
水族館の7割は株式会社です,民間の率が高くて,かなり企業努力をしています。うちの館は,高熱水道費で年間2億,えさ代で2億,それらはみんな入館料でまかなっています。
− 水槽に入れられて魚がかわいそうと子どもから言われたら,どう答えますか。
押し付けはしないけど,僕らがどういう気持ちでやっているかということを説明しますし,水族館にいる生き物にも,野生と違ったメリットがあるということも言います,外敵がいないとかね。押し付けはできない。
学校の先生と授業を作ったときに,そういうディベートの授業を作ったグループもあって,同じ質問で,クラスがちょうど二分された。そこで,水族館の職員が水族館はこうで,野生はこうだ,ということを言って,意見が変わった子は何で変わったのか聞く,
堀田
たまちゃんはどうなんですかね。
流れ着いた生き物の所有権は誰にあると思いますか?勝手にすくって持っていくと,すごい批判を受ける。我々にはそういう権利がない。行政から依頼があって行った,という形になる。つまり海岸の管理をしている行政が,海岸の安全管理の面から,動物が邪魔になるから協力してくれ,ということ。動物を救ってくれという風に要請されるわけじゃない。
堀田
悪乗りしますと,ファインディング・ニモは。商業的に乗っかろうとか,そういうことはありますか。
恥も外聞も無く,と言ってしまうとあれですが,そういうチャンスは逃さずどんどんやります。
ー 学校教育と連携するとき,学校にコンタクトする方法を教えて欲しい。
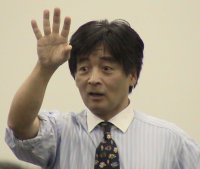 |
高田
一番重要なことは一緒に酒を飲むこと,酒を飲めと言うことじゃなくて,個人的に信頼関係を築いて,お互いに何に困っているかということを話し合えるようになって初めて,うちがこういうことをしますよ,とかいう話になる。そこまでいかないで電話一本で「はいはい」というわけにはいかない。
堀田
是非本を読んで欲しいと思います。そういうことが書いてあります。
学校から見ると博物館は敷居が高いですね。博物館から見るとどうですか。
高田
博物館からは学校が見えない,眼中に無いと言う感じ。
 |
堀田
そういう不可視な範囲にいるわけだけど,でもやってみると面白いことができる。
高田
ずるいことがひとつあって,博物館の教育活動は通知表がつかない,博物館は評価しないんです。でもこれからも評価のこととかそういうことまで関わっていかないといけないんじゃないかと思っている。学校の先生はものすごい真剣で,教師生命をかけて,子どもにどんな力をつけさせるかとか,そういうことを本当に真剣に考えているわけです。だから博物館側でも先生から評価のアドバイスを求められるくらいに職員も踏み込んでやらないといけないと思う。博物館の教育活動も楽しんで終わらせるだけではいけない。
スタッフの人数的な話では,40人の職員がいて,8人が教育的な仕事に関わっている。でも,その人たちだけが教育の仕事をやるだけじゃダメ,全てのスタッフが教育者としての自覚を持たないといけない。組織上は8人だけど,ウチの職員全員が教育スタッフだと言う風に考えないと,いい教育施設にはなれない。
参考文献
講座で紹介された本です。
 |
『博物館をみんなの教室にするために −学校と博物館がいっしょに創る「総合的な学習の時間」−』 堀田 龍也, 高田 浩二 >>amazon |
 |
『教室に博物館がやってきた −社会教育施設と学校をテレビ会議で結んだ遠隔授業の試み−』 堀田 龍也 >>amazon |