■教えなければいけないことは教えない
中村
パワーポイントは大好きだけど,人間の処理能力以上のことを表示させてしまう。だから時々休まないと。どこかの学校の研究発表でも文字ばっかりのスライドを見せられることがありますけどね。今日の授業で子どもが真髄をついたことを言っていた。「○○ちゃんの班は文字が少なくてもわかりやすかった」これが真髄。この○○ちゃんは,詰まり詰まりつまり喋りながらだけど,子どもの脳に届くまでのスピード,そういうものにあっていたわけです。覚えていたことをダーと,立て板に水のごとく喋るだけじゃダメで,相手のことを考えて情報量を調節しないといけない。
中村
それでは始めます。学校で教師が教えると言うことはどういうことか。お金もらうとかそういうことではなくて。学校で学ぶとはどういうことか,そのために教師は何をするか。
中村
総合ではおにぎりを作ろうとか,そういう授業があるが,この現象だけ見れば,子ども達が楽しかったらいいやん,と思うが,この裏にはしかけがあって,子どもが自分で運営しているとか,自分で作った米だとか,はかりで重さを測ったりとか,いろんなこれによって学習するための仕組みがある。その上で,五感に訴えるような,そういうことをやる。
中村
さて。これは掲示物ですけど,自分達で育てた米の粒の重さを3粒はかって平均で出している。こうして,全体の量でサンプルがこうでとか,そういうことに繋がっていくんですが,学習になっていますね。こういうことが学びとつながっている。単なるイベントでは無い,お米を作って終わりではない。大事なのは,学校全体に子ども達を育てる工夫がある。昔は日本の学校は画一的だったが,今は学校ごとにカリキュラムがある。写真は生活科,この学校ではみんなの前で発表することに力を入れている。
中村
ホタルの学習。これは環境問題の学習ですが,実は地域をどうもっていくかということを学習している。6年生になったら提案をしている。6年間で子どもをどうやって持っていくか,発表の能力から提案力。6年間でそうやって育てる。とくに総合的な学習の時間は,学校にカリキュラムが任されているので,そういうことが無いとダメ。
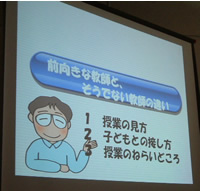 |
中村
まとめです。一番大事なことですが,教えなければいけないことは教えない。子どもがひらめいたように持っていく。「すごいですね!」と言ってあげる。本当に感動したように言ってあげないとダメ,子どもに見透かされてしまいます。ふたつめ,トレーニングの時間が必要。デジカメ一分間スピーチとか,朝のスピーチとか,地道な活動で子どもが鍛えられる。みっつめ,考え方を教えないとダメ,KJ法とか,ブレーンストーミングとか,皆さん知っていますか?そういうことをして,みんなで考えるやり方とかを身に付けさせないとダメ。
中村
授業のいい瞬間を見逃さない。道徳の授業とか,環境学習のときに発揮される。子ども達の感想は「人間のために地球をもっと綺麗にしないといけません」とか言う風になって,普通ならパチパチで終わる。ここで人間のためだけの環境ではないとか,そういう突込みをして,そういう瞬間を見逃さない。子ども達に「なるほど」と言わせないと,先生として認めてもらえない。私は初めは大阪で務めましたが,子どもの反応がすごい,突込みやら逆やらガンガン来るわけです。なので,こっちが上手く切り返さないと,先生として認められない。
中村
人に聞くことをいとわない。自分のことしか見ない先生がいるが,そういう先生に当たると子どもがかわいそう。色んな可能性が奪われる。「わからないけどコンピュータやってみるわ,中村先生教えて」と人に聞くことをためらわないのが大事。もう分かると思いますが,そういう先生は人の中に出て行って勉強しますね。
(休憩)
中村
休憩に食べたチョコレートが甘かったんで口も甘めになってしまうそうですが,この次は少し辛めに。
中村
某浜松市某都田小学校の某先生の教室,荒れてるなー,って違う違う。いい先生はこういう部屋になっている。デジカメ,マビカが置いてあって,プロジェクターがオルガンの上に置いてあったりして,よく使うんですね。黒板消しクリーナー,普通コンピュータのある部屋には無いですけど,ちょっとくらいホコリが被ってもすぐに使えるのが大事。スクリーンもあって,すぐ使えるようになっている。
中村
昼に出た情報部会で聞いたら外れた質問です。なぜ水性のマッキーやユニポスカが置いてあるのか,マジックではなく。これは裏に写らないからですね。この先生は普段から模造紙や画用紙を使って,まとめる活動をしているだなーと,これを見ただけで分かる。マジックだったら失敗する。体育館でやったら新聞紙がどこかへ行って裏写り。先生は校長室呼び出しですね。僕も呼び出されたことがあります。すぐ活動できる工夫を見つけておかないといけない。
中村
浜松市の学校には大体あるのがいいんですが,スクリーン。黒板に貼れるスクリーン。マジックでも書き込める。すぐに活動できる。いい教室。いいところはまだあって,IT教室だけでなくて,ちゃれんじ計プリっこ漢プリっこといった,ドリルがあって,基礎基本もちゃんとやっている。
中村
この間,NHKで授業の特集をいろいろやっていた。調べ学習をしている子どもの机は,盛り上がっているわけです。普通は教科書しか置かないから盛り上がらないんですけど,いろんな資料なんかがある。百科事典なんかが教室に置いていて,すぐに使えるようになっている。家にある百科事典をもってくれば,家も広くなる,子どもも育つ,一石二鳥です。
中村
疑問に思ったらすぐに調べられるサポートも必要。Webが用意されている。浜名湖のうなぎならあるかもしれないが,英虞湾の魚とか行って調べるとどうなるか。知らない地名の魚,でやると,大体ヒット数は0になる。何で引っかからないかということで,先生は子どもに「この中にインターネットに苦手な言葉が含まれています」と言いました。なんですか?
−
英虞湾。
中村
4年生と同じ答えですね。こういわれて先生も困ってました。答えは「の」ですね。「が」とか「は」とかも苦手ですね。「英虞湾 魚」で検索しないといけません。
中村
それだけでいい教師になるかと言うと,そうではなくて,ダメダメ授業を見抜く目がないとダメ。水先案内人と一緒に見るということが大事。そうでないと吹っ飛んでしまう。ここで言うと堀田先生かな。そういう人たちと一緒に授業を見て,一緒に回ると言うことが大事。白い巨頭でも,若い先生は大院長先生と一緒に回診していますね。
中村
ここから私のお勧めダメダメ授業。
これは総合の時間で,おこめについて学んでいる。この班は調べることが前の時間までに決まってなかった。やることがない。先生はこう言った。「農林水産省に送るFAXの文面考えなさい」。この子はうれしい。やることがあって。TTの先生はうんざりという感じ。他の子はもう知らんぷり。子ども達への目標設定が大事。目標がないと,FAXの文面考えなさいと言われても全然必要感が無い。持っていき方がまずい例。総合嫌いを生んでしまう。
中村
うって変わってこの2人はニコニコ。デジカメで撮ってきた農具を取ってきて並べている。いい笑顔,総合の時間が好きなんですね。この2人はこれで俺達の作業は終わった,もうやることが無い,早く切り上げて外で遊びたい,という笑顔ですね。本当は,自分達の考えを書いたりして,調べてきたことをまとめないとダメですから,こういう笑顔を作ってしまうと言うことは,子どもでなくてプリンターが学習したと言うことになるわけです。
中村
皆さん授業ではノートは取っていますか?このごろポートフォリオというノートが流行りになっている。集めてきたことを放り込んでいるノートみたいなものですね。集めてきたものと横に自分の考えを書き込む場所がある。この例は自分の考えや思ったことを書き込んでいない。こういうのはポートフォリオと呼ばない。ただの紙ばさみと言います。
中村
自分達の意見をしっかり模造紙に書き込んでまとめようというグループ。ひとつだけ欠点がある。この班はH班と言う。なぜH班か。この班はお米の歴史を調べている。なぜH班なのか,僕は気付くのに30分くらいかかった。HistoryのHなんです。先生がつけたんだと思いますが,子どもはわからない。何を調べているかがわかるようにしないと,他の班との連携が取れない。学校で学んでいる意味がない。テーマやネーミングは大事になっている。
中村
そうこうする間に,授業も終了。10分前に集まってきて,皆で情報を共有しようという段になりました。女の子が代表して発表している。ここに欠点がある。なにが悪いのか。これだったら,先生にしか話していない,全然情報の共有になっていません。前に出てきて説明しないと。子ども達に意見を言わすときには,机をコの字型やロの字型にします。あるいは班ごとの島型にしたり。そうでないと1対40になってしまいますから,ちょっとした工夫だけど,こうやると盛り上がります。
中村
Yahooで「お米」といれて検索している。膨大な量がヒットする。この子たちは30分立ってもカチカチとマウスの練習している。検索は難しいので,先生がリンク集を作るとかしたほうがいい。
中村
インターネットで印刷した籾殻の絵を画用紙に写している。綺麗に写しているが,これは図工の時間ではない。暗記ではないので,写して,胚がどこで,何がどこだとかそういうことを覚える必要はない。それは調べればいい事で,どんな力が伸びるのかということを考えて,先生は手を入れないといけない。
中村
調べ学習をしています。インターネットで調べたものを模造紙に写しています。ここで初めて図書の本が使われている。インターネットで調べるだけでなくて,資料集や図書や新聞も大事ですね,と言われています。わかりますか?模造紙が丸まってこないように,重しとして図書の本が役に立っています。お米についての資料を使うときには,よさやメリットを感じさせるために色んなメディアを体験させることが大事になってくる。資料集だったら上手く図版や絵になっているので,よく分かるとか。そういうことを体験させるのが大事。ここでもパソコンの印刷を移すのが学習になっていましたね。
この子たちは何をしていたのか。農林水産賞にFAXの文面を考えていた。おかしいところがある。FAXの文面を考えるのに,コンピュータ室に来る必要がないですね。しかも話し合いにくいですね。30分たって,2行書けました。「拝啓農林水産省様 お米について教えてください」,これ本当に送りました。20枚くらい返ってきました。向こうの役人も暇じゃないですから,もう少し考えて欲しいですね。話し合いが出来ているか,作業の分担ができているか,文面を考えるのが大事なんじゃなくて,何を聞くかが大事だから,FAXのヘッダの部分は教師が考えておく必要があります。