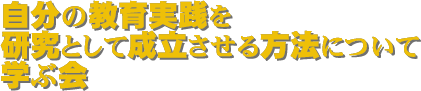トップ > 公開検討会1>公開検討会2>公開検討会3
>ミニ・トークセッション
ミニ・トークセッション
「教育実践を研究にするのは何がどう難しいのか」
堀田
ここからはミニトークセッション。何がどう難しいのかを確認しあう。僕がいろいろ聞くと言う感じで進めます,途中フロアの悩み,「皆さんのこういうところが難しいと思っています」ということを話題にしたいと思います。研究仕立てにするにはどうしたら良いかと言う話をしたら,木原先生の講演につなげます。
今日の発表者3人の人は,第一回選択希望選手というメールを出して,すぐに返事をした人。返事をしてしまってから悩みだした,と言う感じ。3人みんな学会発表にするところまで行くと思うけど,まとめ方に難があった。これは現場の先生が学会発表するときにはありがちなパターンで,僕もそういうところに何度も陥ったことがある。普段の実践をする筋肉と違うと言うことがある。
どこが難しいのかと言う話をする。
皆川先生の発表のロジックは,交流すると言うことが試合数の増加をもたらして,級があがったと。交流したから,試合数が上がったと言うとことにクエスチョンがつきました。
山内
先生は子どもを見ているので補完情報が入っている。身体に入っているのでそう書いちゃう。研究が難しいのは,書かれたもので勝負しないといけないところ。書かれてないと分からないし,書いてあっても,あなたの思い込みだろうと言われちゃう。
堀田
これは企業の人が,さも自分のところの商品をいいものだということと似ていますか。
山内
そうですね,嘘はついてはいけないし。でも企業の人は上手く行かなかったところは言わない。研究では都合が悪いところも,他の人の役に立つと言うことがあるので,それには価値がある。
堀田
実践が上手く行かなくても,研究として上手く行くところがあると。
因果関係に結びつけると上手く行かないと言うのは勉強になります。
正來先生の発表では,ワークショップをしたしたというけれど,その方法が,今までの授業とどこが違うのかというところを,手続き上書かないといけないということでした。小柳先生の周りでもこういうところで悩む先生はいますか。
小柳
やはり正來先生のように努力されている方が多い,なさっていることも濃い。ただ,それを表現するときに,書き忘れがある場合がある。ワークショップは流行っているが,日頃の授業の中のグループ活動と何が違うのか。ワークショップを使うとグループ活動と何が変わるんだ,ということが分かりにくい。ただ,何かやってくれそうだと言う期待はあるわけです。その思いを語られたほうがいい。ちょっと変えてみたいということをするが,言葉足らずで,せっかくのオリジナリティがよく見えなくなってしまうこともある。
堀田
それはどうすればいいでしょうか,誰かに聞いたほうが良いのか
小柳
こういった機会もあるし,教育工学雑誌の実践報告なんかがどうか書かれているかを見たほうがいいかもしれない。紙面の都合上,4ページしかないから,絞って書かれている。どの部分を殺ぎ落としても大丈夫かが読み取れる。
堀田
現場の先生が発表しようと思ったときに,場はだいたい二つ。一般的には去年沖縄で開催された教育工学協議会,というやつと,去年は岩手で開催された教育工学会。どっちかというと,協議会には皆さんと同じ症状の人が集まる。論文集と書かれているのは,正式には発表予稿。論文と言うのは,差読者が査読して,認められたものが教育工学雑誌というのに載っている。もちろんわからないものもあると思うけど,サプリメント,増刊号みたいのに,実践報告が載る。
たぶん,僕も含めてそうだけど,その領域のことを知らなさすぎる。例えばワークショップの本をどのくらい読んだのか。さらに,もしかしたら正來さんの研究は,付箋紙に書くことが及ぼす効果かもしれないし,付箋紙をまとめるのが及ぼす効果かもしれない。もっとちゃんと勉強したほうがいい。
ここでちょっと皆さんに,今度学会発表したいと思っている人に,実際に研究するときにどこが苦しいのか,聞きましょう。
五十川
見通しを持ってなかったので,取るべきデータがわからなかった。もうひとつは自分のやることが研究になるかどうか分からない。
山内
だれかに相談するのが一番。順番があると思うけど,これが研究になると思ったら,自分で調べて,大事なのは学会誌,論文のようなもので書かれてないか。あと領域の話,自分と近い領域の人がすでにやっていないかどうかということ。余裕があれば学校研究の紀要。他に前に誰か似たようなことをやっていないのかと言うことを調べないといけない。他の人を参考にしながら自分を位置付けることができるようになってくると思うけれど,この段階で誰かに持っていくと,具体的な建設的なコメントができると思う。
堀田
最初の段階をやるときに,調べることができない。論文集が手っ取り早いと思うけど,白江さんので言うと,スピーチと言うのは誰かがやっている場合がある。でもきっと白江さんのとは違うはず,前に人がいた方がやりやすい。この人はここでこうやっていますが,私のはこうですと言える。見つからない場合は,本当に新しいことか,やる価値が無いことかどちらか。
山脇
自分も実践を研究的にやりたいと思うが,これがどの部分に,実践を切り取って良いかわかりにくい
堀田
どこをどう取り出せばいいか分からないということですが
小柳
皆が悩んでいること,実践が厚くなればなるほど迷う。自分の信念は信じないといけない。自分の問ってなんなのかを問う。それは大事にしないといけない。自分が追い求めたいものは何か,全部殺ぎ落としても残るのは何かを考えたほうがいい。どこを切り取っていいか分からないというときには物に当たったほうがいい。
今は雑誌記事索引と言うのがあって,そこに当たると,キーワードにヒットした論文が出てくる。本当はフリーで使えると良いけれど,ほとんど有料で,多分静岡大学とかでは法人で一括契約しているので使える(堀田:僕の研究室に来ると検索できます。)。いろんなところに行ったところに,キーワードでいれて検索していると,同じ名前が出てきたりして,それからその人が継続的に何を追っているかと言うことを2年とか3年とか長いスパンで見つめてみると,取り方の方法が見えてくる。
一番良いのは自分の信念。もうひとつは,一番近い人を見つける。その人が追求していることを,雑誌記事とか,そういうものを切り取って,手時かなライバルと言うか,モデルを見つめたほうがいい。
堀田
教育実践が複雑なのは宿命。実践が終わって,最後になって,さあやるか,というと,もうほぐせないものになっている場合が多い。
1度目は苦しむけれど,次には研究的実践ができると思う。3回とも来ている人。
藤原
僕はよく言われるのは,小さくまとまっていくと言うのが欠点。どんなデータを取ったら良いかわからなくて。先を見通す力が無いので,データが取れるのが短い時間で,小さくなってしまう。
堀田
綺麗にデータは取れるんだけど,データを取れたのが3時間分とかで,セコくなってしまうという悩みです。これからどうしたら良いかのお導きは講演で。
僕は,1回きちんとくぐった人は,2回目以降ずいぶん楽になっている印象を受ける。1回目の発表が一番大変。正來さんは2年続けて発表したけれど,2年目は楽でしたね。1年目は何が大変なんだろう。
正來
結局のところ何が言いたいのか自分で分かってない。結論を持っていなかった。
堀田
この実践のこれと言うのは決まっているが,何を明らかにするかを明確にしないで,ディテールばかり話している。例えばワークショップは何でやろうと思ったの。
正來
正直おもしろそうだったというのが動機。
堀田
本当の動機はともかく,研究として書くにはどうしたらいいか。
小柳
これは難しいですね。どう研究に仕立てるかと言うとき,その前に立場と言うものがある気がする。同じ研究をするときに,授業者としての教師,観察者としての教師,両極の立場があるとして,観察する授業者,授業する観察者と言うのもある。授業する観察者は,授業しているけれど,最終的には自分のかかわりをあまり入れない。そういうことを考えるときに,自分が授業していて,そこを研究するのが(記録者注:うまく取れませんでした)
ある場面では,観察に徹する授業者になってみようとか,もうひとつは授業をしつつ観察するというか,ある種,立場そのものを変えてみたらひとつ同じデータを取ってみても違うのではないかと思います。
堀田
自分の研修と言うか,そういうトレーニングはどうかと言うことですね。
小柳
そうすると今までと違うスタンスになるので,違うものが得られると思う
堀田
僕らは職業として研究している。人の論文でもこう書けばいいと言うセオリーがある。他の人の実践を読んだときに,こう書いたら論文になるな,というそういうセミナーみたいなものをやると面白いなと思ってます。実際に企画するかどうかはこれから考えるとして。
山内
小柳さんの行っていることは正攻法。なんだけど,教育実践研究の場合は,結構皆嘘つきな部分もあって。ここは割り切ったほうが良くて,語弊がありますが,ロジック的に正しければ嘘を突いても構わない,と思います。10秒スピーチは面白そうだからやったと,たまたまやったら別のところで大当たりしたと言うことは,教育実践ではよくあること。せっかく面白いことが出来たのでそれを研究したいと思うのも人情としては大いに理解できる。だから嘘をついてもいいと思うわけです(記録者注:実践の論理展開と研究上の論理展開の面で)。面白かったとおっしゃった。何で面白かったのかと言うことを考えて,今までやられてきた取り組みと何が違うのか考えて,例えば10秒スピーチなら,カリキュラムにしたら上手く行ったというのがある。そこから調べる。そこで自分の研究の目的に据える。実践はやっているが,そこから考えて論理を作ると。ディベートを考えてもらうと分かるが,勝ち負けとかじゃなくて,論理的な整合性が問題。
堀田
それに決めたらあとは捨てると言う勇気と言うか,そこをしないとぐちゃぐちゃで論が通らない。最初から光が見えて,それをずーっとやっていける人はともかく。最初は色々やっていって,そこでこれがいけそうだと選んで,そこから逆算して,そのラインだけやっていくと言うか。
ひとことに研究といっても色々あって,何が起こったのか,と言うことだけを研究している人もいる。自分の研究のタイプは難だろうな,ということを考えた方がいいですね。でも皆さんプレイヤーなので,違う方法を持ち込んだときに,それが上手く行くと言うことを実証したほうがいい。問題は今までの方法では上手く行かないと言うことを示さないといけない。
悩みが分かったところですぐにできるわけではないので,僕はこのセミナーを毎年やっている。リピーターがこれだけ付くのも継続することで分かってもらえることがあるんじゃないかと思います。
|