horitan のすべての投稿
AIによる物体検出における学習させる条件による靴の検出の精度の違い
不正行為の有無による受験者がCBT受験時に見ていた対象物の違い
小学校高学年の児童が探究の過程における「情報の収集」の段階でチャットを利用した際の特徴及び影響の検討
第79回ゼミ(オンライン開催):2023/02/19(日)09:00-11:00
毎回,日曜日のゼミ開催ですが,本日は午後から東北大学大学院情報科学研究科の30周年記念シンポジウムがあり,堀田先生と長濱先生の講演等があり,あわただしい1日となります。
そんな本日の午前中ゼミは,堀田先生と川田先生のご指導のもとオンラインで実施され,現役ゼミ生として中川,渡邉さん,OB・OGとして八木澤さん,中尾さん,阿部さん,遠藤さん,小田さん,村井さん,槇さんが参加しました。年度末の時期ということもあり,OB・OGの異動等のおめでたい情報共有がいくつかありました。
ゼミの内容は,現役生の人数が減りOB・OGの人数が増えていることもあり,個々の研究に対する指導に加えて,各自が推進する研究に関する情報共有が多くなってきています。ゼミが研究のペースメーカーとしての役割に変化しているように感じています。OB・OGの報告を聞きながら,自分も研究のペースを保つ「研究者としての自己調整」が重要だと感じました。堀田先生からは「どんなに能力があっても,努力しない人,毎日努力を続けている人には結局敵わない」とのお言葉をいただきました.
次回ゼミは千葉大学で対面での開催を予定しており,ゼミの皆さんとお会いできるのをとても楽しみにしております。
(報告:D3中川)


クラウドでの共同編集機能を用いた学習指導案の検討作業の特徴 −中堅教師による若手教師への指導場面を対象に−
クラウドに関する理解と体験の学習順序が小学校第3学年児童のクラウドを主体的に活用しようとする意識に及ぼす影響
コネクティビズム(Connectivism)に関するレビュー
画像認識についての学習による小学生のAIに対するイメージの変容についての検討
教育DXで学校はどう変わるのか
A Trial Study on Understanding Operational Tendency of Device Use Based on Operation Logs during Home Study Using Japanese Authorized Digital Textbooks
デジタル教科書を活用した授業づくりの考え方
第78回ゼミ(オンライン開催):2023/01/08(日)09:00-11:45
2023年になって初めてのゼミもオンライン。現役ゼミ生2人とOG・OBが6人,堀田先生,長濱先生,川田先生と合わせて11名の参加でした。
現役ゼミ生のうち1名はもうすぐ博論提出。修了後に残る一人,つまりわたしのために細かなことまでアドバイスをくださいました。OG・OBの皆さんが一人ずつ修了されることは嬉しい一方で,寂しくもあります。しかし,先輩方が有形・無形で修了までの道程を残してくださることは本当にありがたいことだと思っています。
また,OG・OBの皆さんがゼミに参加してくださることにも感謝します。単に参加してくださるだけでなく,それぞれが取り組まれている研究について,報告してくださいます。今回のご報告も盛りだくさんの内容で,現役の身も引き締まりました。
そして,ゼミの最後には「HORI BUDDHA」に3段目と4段目の階段が追加されました。
干支の兎のような大きな飛躍はできないかもしれませんが,今年も研究の歩みを確実に進めていきたいと思います。
(報告:D3渡邉)

学校と教育委員会・自治体をつなぐ教育DX推進ガイド
Characteristics and Cognitive Processes of Teachers’ Test Scoring in Japanese Elementary and Secondary Education
児童のICT操作スキルに関して教師が行う支援の経時的な変容の調査
高校数学における個人特性とCBTパフォーマンスに関する試行的検討 -数学のエンゲージメントに基づいたケースの分析-
スマートグラスを用いた楽器演奏支援システムの開発と評価の試み -姿勢・視線・演奏の主観評価から-
写真を読み取る力の育成を目指した小学校第6学年児童向けの学習指導とその評価
1人1台の情報端末を活用して子供主体の学習を目指す授業における教師歴の影響による児童の学習活動と教師の発話の分析
学習方法を自己選択する授業の経験と学習方法のメタ認知の関係 -学力の高低ごとの検討-
授業中の教育実習生に参観者が助言や励ましを送信可能なシステムの開発と評価
大学生のSDGs教育のためのワークショップのデザインと評価
日常生活や社会との関連を図るアニメーション教材の開発と評価 -小学校第4学年理科「物のあたたまり方」での実践を通して-
コンピュータサイエンス教育におけるジェンダーに関する日本と諸外国の先行研究分類の試み
中学校英語科デジタル教科書の家庭学習時の操作ログに基づく端末利用の実態把握の試行的検討
コネクティビズム(Connectivism)に関するレビューの試み
LEAFシステム導入による小学校教師の授業設計・展開の変容に関する一検討
メディアが伝える情報の信憑性を意識させるための小学校第4学年児童向けの学習プログラムの開発と実施
OGの村井さんが日本教育メディア学会論文賞を受賞
OGの村井明日香さん(現・桜美林大学・非常勤講師)が,日本教育メディア学会で論文賞を受賞しました。
この賞は、論文誌『教育メディア研究』に掲載された論文の中から,優秀な論文の執筆者に授与される学会の賞です。
以下の研究発表が受賞の対象となりました。
村井明日香,浅井亜紀子,宇治橋祐之,齋藤玲,堀田龍也(2021)
テレビ・ドキュメンタリーに対する番組制作者と大学生の意識・態度の違いに関する調査研究
教育メディア研究 28巻1号 pp.13-31
受賞関係記事:
https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/activity/award/detail—id-1268.html
「ICTの効果的な活用」の考え方を再考する
技術科の実習指導における指導の個別化のための映像教材の作成と実践
Characteristic of the Teachers’ Teaching Knowledge of One-to-One Computing in Elementary Education Classes
第77回ゼミ(オンライン開催):2022/11/13(日)09:00-11:00
第77回ゼミが開催されました。
ゼミはオンラインで行われ,堀田先生,長濱先生からご指導をいただき,参加者は,D3中川,D3渡邉さん,OB・OG 阿部さん,遠藤さん,安里さん,小田さん,八木澤さん,中尾さんでした(発表順)。
まずはじめに,堀田先生より,ゼミ参加者が関係する学会や講演会等の情報共有が行われました。2022/12/03にはJSET22-4@鹿児島女子短大(渡邉さん勤務校),2023/03/18にはJEAMS第2回研究会@広島経済大(後藤さん勤務校)が計画されており,堀田研関係者が自分の研究だけでなく,学会運営に協力・参画している様子を共有いただきました。
その後,現役ゼミ生の研究進捗報告とOB・OGの活動報告が行われました。ゼミ生の報告では,方針が決まらなくて悩む時間を多くとるより,いったん「たたき台」を書いてしまって,ブレストを行ったり,指導をもらったりすることの重要性をご指導いただきました。特に,完成度が高まっていない状態で,情報共有し,厳しいフィードバックをもらうのは心理的にもつらいことではあるが,そのほうが,最終的にはダメージが少なくなる”Fail First”についてお教えいただきました。
また,いつも,OBOGの皆様がご参加いただき,研究の様子をお教えいただけることは,研究の効率的な進め方を知れるだけでなく,われわれゼミ生の研究の励みとなっております。ありがとうございます。
(記録:D3中川)

のこぎり引き動作の特徴をスマートウォッチとAIで判別する手法の提案
大学生がビジュアルプログラミング言語を使用する際の視距離の傾向
CBTにおける視覚利用型不正行為の有無による視線運動の違い
小学校第6学年算数科の教科書における記述内容の形式と役割の分類に関する調査
児童生徒の「クラウド」に関する知識と家庭における情報機器利用との関連の分析の試み
メディア特性の理解を基盤とした情報の信憑性を検討する学習の実践と評価 -小学校第6学年の総合的な学習の時間における平和学習の実践を通して-
1人1台の情報端末を活用した授業において必要となるメディア・リテラシーと関わる教育的内容知識の内容項目の検討
タブレット端末で360度画像を用いる際の操作方法の違いに対する児童の評価
情報科教師が有する「授業についての知識」の枠組みの概要
ウェブ情報の収集に関する教師による学習中の支援と児童のメタ認知の関連の検討
1人1台の情報端末を活用した個別最適な学びを始めるための小学校教師用チェックリストの検討
小学校第6学年を対象としたAIの画像認識について理解する学習プログラムの開発・実践・評価
第76回ゼミ(オンライン開催):2022/10/16(日)09:00-11:00
9月に博士後期課程1名が修了し,現役ゼミ生は2人となりました。ただし,修了したばかりの方をはじめとして4名がオブザーバーとして参観してくださり,堀田先生,長濱先生,川田先生と合わせて9名の参加となりました。
ゼミは今回もオンライン。ただ,今後のスケジュールの確認では,大学のイベントやメディア教育論ゼミの対面開催が計画されているとのこと。青葉山キャンパスに行くことや,ゼミの皆さんと直接会えることを,心待ちにしています。
現役ゼミ生のうち1名は予備審査への追い込みとなっていて,これからタイトなスケジュールへと突入です。オブザーバーの皆さんも,各自の本務を果たしつつ,研究を進めていらっしゃいます。大学教員の仕事についての話題では,堀田先生が教育工学に関わることになったきっかけに話が及び,ビックリでした。
自分としては,研究に関するディスカッションが十分とは言えません。Slackで情報発信するなどして,堀田研の皆さんとコミュニケーションを取りながら,前進したいと思います。
(報告:D3渡邉)

最新教育動向2023 -必ず押さえておきたい時事ワード60&視点120-
情報モラルに関わるCBTに日常的に取り組んでいる学級におけるeラーニング教材への取り組み方の特徴
日常的に情報モラル教材に取り組んでいる小学校第6学年の2学級におけるCBTに取り組む順序に関する分析
中学校理科における細目積み上げ式テストの設計と項目別正答率による生徒の理解度把握の試み
1人1台端末の活用を校内において推進するキーパーソンの業務および推進に関する工夫の調査
クラウド上のスプレッドシートで記述した児童による授業の振り返りの傾向の分析
情報教育のテキストを用いた小学校段階の情報活用能力育成の取り組みやすさ等に関する調査(2) -テキスト活用の前提の有無での比較-
アクセスログからみたGIGAスクール構想1年目の情報モラル教材の利用傾向
クラウドサービスの共同編集アプリを用いた肯定的な相互コメントが小学校高学年の児童の自尊感情に与える影響
An Experimental Application of a Real-Time Pitch Feedback System for Performances with a Conductor’s Indication
教科書におけるQRコードの利用に関する実態
エラーで学ぶScratch -まちがいを見つけてプログラミング初心者から抜け出そう-
のこぎり引きの試行の有無がのこぎり引き技能の習得に対する自信に与える影響
のこぎり引きの指導におけるラーニングアナリティクスツールを用いた支援の効果
An Introduction of Musical Performance System using Google Glass
Practice and Effects of Programming Education using Drones in the Agriculture Unit of the Fifth Grade of Elementary School Social Studies
第75回ゼミ(オンライン開催):2022/09/04(日)09:00-11:30
第75回メディア教育論ゼミは,堀田先生,長濱先生,川田先生,現役ゼミ生3名,OB・OGの合計12名が参加しました。
残り少ない現役ゼミ生も学位取得を間近に控え,博士論文の具体的な進め方や,博士論文の先行研究に何を引用し,それを,これまで取り組んできた研究にどのように結びつけるかといった,博士論文における理論の位置付けに関するアドバイスが行われました。
私は8月に博士学位論文の最終審査を終え,今回が現役としては最後のゼミの参加となります。堀田先生からは研究者としてのアイデンティティの確立が必要であるとのアドバイスをいただきました。博士課程修了後も,継続して社会における自分の役割を見定めながら,自分自身の研究者としてのアイデンティティを模索していきたいと思います。
最後に「HORI BUDDHA」に2階目の階段が追加されました。階段が追加されるたびに選ばれる今回のほりたん語録は,「ゼミは,強い個の集まりであるべきです」でした。堀田先生からはその意味として,研究は共同で行うとしても誰かが責任を持つといった強い個が必要であるとともに,強い個だけでは研究が広がらない。メディア教育論ゼミでは一人ひとりが強い個の集まりであると思いたい,ということをお話しいただきました。
(報告:D3小田)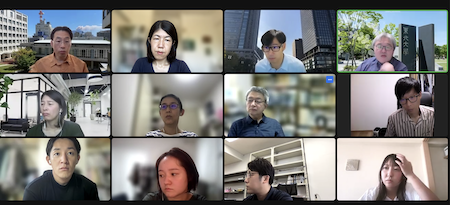

1人1台情報端末の環境下におけるクラウドを用いた学校間交流学習の試み(2) -児童の振り返りの文章の分析-
1人1台情報端末の環境下におけるクラウドを用いた学校間交流学習の試み(1) -児童の共同編集の経験を踏まえた実践の設計-
写真を読み取る力の育成を目指した学習指導を繰り返し行うことによる個人内の変容に関する考察
1人1台端末を前提とした「学習の個性化」を目指す授業の設計・実施・評価の際の検討事項 に関する調査
1人1台の情報端末でウェブ情報にアクセスしている児童によるウェブ情報の収集方法に関する振り返りの分析
学習指導要領解説における統計的リテラシーに関する項目の分類 -中学校社会編及び理科編の分析を通して-
校内研究を対象とした研究の学習指導要領改訂前後の動向
1人1台の情報端末を活用した授業に関する研究の実態把握
AIの骨格検出技術を用いた体の大きさとカメラの画角に依らない視距離推定手法の提案
発言をききながらコメントを入力する学習活動に対する児童の意識に関する検討
OBの板垣君が学会賞をダブル受賞
OBの板垣翔大君(現・宮城教育大学・専任講師)が,2つの論文賞を立て続けに受賞しました。
○日本産業技術教育学会学会賞 論文賞
この賞は、特に優れた研究をなし、その業績を日本産業技術教育学会会誌に発表した者に与えられるものです。
板垣翔大,千田優花,阿部博政,安藤明伸,堀田龍也(2021)
スマートデバイスとAIの骨格検出を用いたのこぎり引き動作の学習の実践と評価
日本産業技術教育学会誌,第63巻,第3号,pp.371-378
受賞関係記事:
https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/news/award_p/detail—id-1230.html
○コンピュータ利用教育学会学会賞 論文賞
この賞は,コンピュータ利用教育学会の会誌に論文を発表し,コンピュータ利用教育の発展に独創性および将来性をもって寄与したと認められる者に与えられるものです。
板垣翔大, 浅水智也, 佐藤和紀, 中川哲, 三井一希, 泰山裕, 安藤明伸, 堀田龍也(2021)
AIを活用したプログラミングを取り入れた授業が中学生のAIに対する意識に与える効果
コンピュータ&エデュケーション Vol.51 pp.58-63
受賞関係記事:
https://www.is.tohoku.ac.jp/jp/news/award_p/detail—id-1232.html
初等中等教育における筆答テスト採点支援システムの作業面と学習指導面の特性
小学校の総合的な学習の時間におけるプログラミングによる地域の課題解決を考える学習の実践と効果の検討
1人1台情報端末やクラウドを日常的に活用している学級における授業の分析の試み
オンライン夏合宿(第74回ゼミ):2022/08/06(土)~2021/08/07(日)
第74回ゼミは,今年で8回目となる恒例の夏合宿でした。今回は,当初,山形・河北町で宿を貸し切っての対面開催を計画していましたが,新型コロナ感染拡大(第7波)の影響で,オンライン開催に変更しての実施となりました。
合宿参加者は,堀田先生,長濱先生,川田先生と立花さん,現役ゼミ生3名,OBOG13名,講師として小柳先生@関西大,高橋先生@学芸大,柴田・田島先生@東海大,泰山先生@鳴門教育大,小島先生@奈良教大,三井先生@山梨大,小柳研@関西大ゼミ生2名,佐藤研@信州大ゼミ生3名,板垣研@宮教大ゼミ生1名,長濱先生の出身研究室(森田研@早稲田大)ゼミ生1名,彦田先生@興南中高の総勢35名でした。
現在の堀田研は,OBOGが多く,D3学生が3名(うち1名は,博論予備審査と博士論文提出を終えて,最終審査直前)という構成に変化しています。そこで,夏合宿の企画運営については,前回までのようにゼミ生を中心としたものではなく,今回からOBOGが中心になって進める形に変化しました。ご担当OBOG各位,ありがとうございました。
夏合宿の内容についても,これまでの夏合宿で中心的に行われてきた堀田研ゼミ生の博論研究に対する討議に加え,関係研究室ゼミ生の研究討議やOBOGの現在取り組んでいる研究報告が行われました。さらに,大学教員になられたOBOGから,大学教員として様々に取り組んでいる事柄についても情報共有いただきました。
講師の小柳先生からは,研究者,かつ,大学教員として取り組むべき内容や構えについてのご指導をいただきました。また,高橋先生からは,総括として,堀田研という基盤の上に,堀田研で博士号を取得した研究者が,自分らしさをどのように確立していくのかについてのヒントをいただきました。講師の先生方,ありがとうございました。
堀田研夏合宿の実施形態や内容は変化しましたが,目的は変わりません。堀田先生から冒頭で,夏合宿の目的(1.各自の研究を説明し,2.自分の研究がどのように見え,何が伝わらないかを知り,3.他者の意見を取り入れ,4.研究内容/方法/新規性/社会的価値を確認,5.研究のセオリー習得,6.先人の努力に学ぶ,7.縦横のコミュニティ形成)をお示しいただきました。今,夏合宿を終えて,それぞれの参加者が目的を達成できたかを振り返りつつ,今後の研究につなげてまいります。
(報告:D3中川)
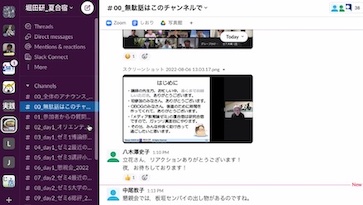

PPDACサイクルを活用した統計的リテラシーの育成の効果について -PPDACサイクルを2度回すことを重視した授業展開を通して-
A Study on Critical Thinking on Biased Web Information among Sixth-Grade Elementary School Students in Japan
第73回ゼミ(オンライン開催):2022/07/10(日)09:00-10:40
第73回のメディア教育論ゼミは,現役3名と,堀田先生,長濱先生,川田先生,OG・OBなどオブザーバー4名の計10名の参加で実施されました。
博士論文の予備審査を終えたゼミ生と,これから本格的に博士論文を執筆するゼミ生の報告を受けて,堀田先生から「まず何も見ずに頭の中にある情報だけでプレゼンを作ってみること」というご指導がありました。プレゼンを一から作ることで,ロジックを通すことができたり,自分でできていないところが分かったりすることや,プレゼンを先に作ることで,結果を見通すことができることなどを説かれました。博士論文も予備審査も,一つ一つの研究とその発表も,「こういうことが言いたい」と見通しをもって進めることができるようにしたいと思いました。
ゼミ生の進捗状況の報告だけでなく,オブザーバーの皆さんの近況や研究の報告,今後の計画も刺激になりました。
次回のゼミである夏合宿の予告もありました。久しぶりに対面で開催できることを切に願っています。
(報告:D3渡邉)
児童が情報端末を活用する授業における授業設計時の教師の作業とその手順に関する実態把握
360度画像と3D画像の特性を踏まえた活用方法の検討 -小学校第6学年理科「土地のつくりと変化」での実践を通して-
平成29年告示小学校学習指導要領におけるメディア・リテラシーに関連する記述の分析
小学校第6学年を対象としたAIの画像認識について理解する学習プログラムの開発と効果の検討
クラウド上のスプレッドシートを利用した授業の振り返りに対する児童の意識の分析
1人1台情報端末環境でGoogle Workspace for Educationを活用している中・高学年児童のICT操作スキルの実態調査
Identifying Latent Traits of Questions for Controllable Machine Generation
A Pilot Study of the MVP Support System using Google Glass
Investigation of Motion Capture Methods Using Video Cameras: Trial Analysis of Movements during Practice of Playing Musical Instruments
GIGA完全対応 学校アップデート+
メディア・リテラシー教育の初心者教師による1人1台の端末とクラウドを活用した実践の試行
小学校理科「すがたを変える水」の温度測定におけるプログラミングを活用した授業の実践と評価
クラウドでの共同編集機能を用いた学習指導案の検討作業における教師の意識の分析
第72回ゼミ(オンライン開催):2022/05/15(日)09:00-11:00
第72回メディア教育論ゼミは,堀田先生,川田先生,現役ゼミ生3名,OG・OBなどオブザーバー6名の計9名がオンラインで参加しました。現役ゼミ生からは,それぞれの進捗に応じた研究相談を行いました。学術的な知見に寄与するために,どのように博士論文を骨太にするかという点や,研究における自分のブランディングの重要さに関して堀田先生からアドバイスをいただきました。
ここ数ヶ月は,現役ゼミ生よりもOG・OBの参加の方が多くなり,メディア教育論ゼミの在り方も変化しつつあるように感じています。これまでは現役ゼミ生が中心となり研究の進捗を報告して,堀田先生のご指導を受けながら学ぶことが中心でした。一方,現在では多くのOG・OBの参加により,現在だけでなく少し先の未来を見ながら,研究を進めることができるようになりました。今回参加した6名のOG・OBのうち3名は,今年の4月から大学の教員として新たなスタートを切っています。大きな環境変化があった中でも研究を続けている姿勢に刺激を受けました。大変ありがとうございました。
最後に,第68回ゼミで30本目のリボンを結び役割を終えた「ほりたん神社」に代わり,今回から次世代の「HORI BUDDHA」が始動しました。「HORI BUDDHA」は,足場となる板に論文名を記載し,足場と垂直な面にほりたん語録を印字した板を追加していくことで,階段が1段ずつ増えていく仕組みになっています。もちろん板垣さんの作品です。
今回のほりたん語録は『大事なことは「不言実行」ではなく「有言実行」』でした。堀田先生からは,その意味として,目標を立てるという点で意味があること,実行したいことを仲間に話すことで周囲に手伝ってもらいやすいということをお話しいただきました。
(報告:D3小田)

Analysis of K–12 Computer Science Curricula from the Perspective of a Competency-Based Approach
小学生と大学生を対象としたクラウドコンピューティングに関する知識の調査
第71回ゼミ(オンライン開催):2022/04/10(日)09:00-10:35
3月に院生2名と研究生1名が修了し,4月から現役ゼミ生が3名になりました。第71回のメディア教育論ゼミは,現役3名と,堀田先生,長濱先生,川田先生,OG・OBなどオブザーバー4名の計10名の参加で実施されました。
この4月にゼミのOG・OBの皆さんで大きく立場の変わった方も多く,その紹介からスタート。ゼミ生の研究の進捗報告では,査読論文と博士論文の関係や統計処理のトレンドなどが話題になりました。また,オブザーバーからも,研究生の修了報告や最近の取り組んでいることなどの近況報告がありました。
これからのゼミでも,堀田先生・長濱先生・川田先生からはもちろん,OG・OBの皆さんからも学び続けていきたいです。
(報告:D3渡邉)
