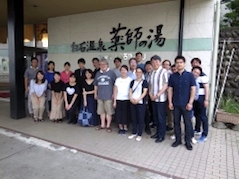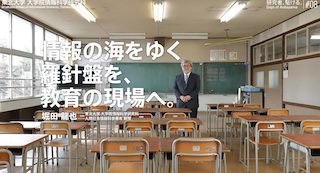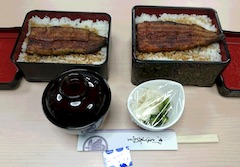本日,第37回のメディア教育論ゼミが行われました。今回のゼミはゲストを含め12名の参加でした。今回,堀田先生が体調不良でご欠席ではありましたが,Slack上でリアルタイムの御指導をいただきながら,緊張感を保ちつつ,自主的に進めることができました。
まず,本日の進め方について進行から説明があり,その後,院生それぞれが進捗状況を発表し,質疑・意見交換を行いました。今回は,進行と記録をそれぞれで分担しながら進める形式で,お互いに役割を分担しながら進めることができました。院生全員が発表に対して質問や意見を行い,研究テーマに対するそれぞれの思いを語る場面もあり,積極的に参加できたと思います。また,Slackを通して,堀田先生から途中途中に的確な御指導をいただきながら,それぞれの研究への考察を深めていくことができました。
ゼミ終了後は,恒例の「ほりたん危機一髪」なのですが,今回のゼミでは,論文の採録に関する報告が無く,危機一髪は実施できませんでした。このような状況は初めてのことでした。ゼミの目標である査読論文50本まであと1本ですから,今後,しっかり頑張らなければと全員が決意したところです。
ゼミ終了後は,恒例の鰻をいただき,いつものようにゼミを終えました。
(記録:D1山本)